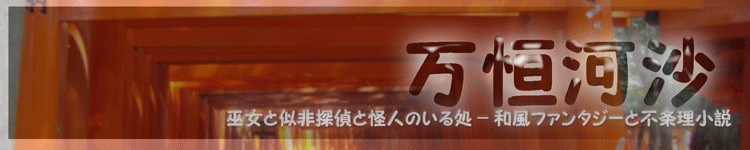
|
| ご案内 | オフライン | さかきちか創作部屋 | ツカノアラシ創作部屋 | LINK | 管理人日記 |
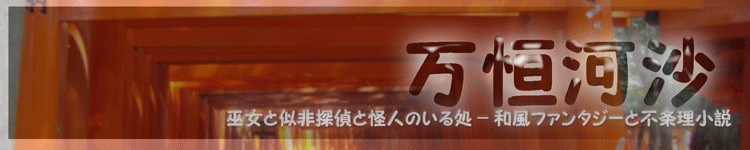
|
| ご案内 | オフライン | さかきちか創作部屋 | ツカノアラシ創作部屋 | LINK | 管理人日記 |
|
白雪と探偵其の一 探偵事務所に小悪魔登場の事、並びに探偵が娼館『少女屋』を舞台にした奇妙な事件に巻き込まれる事。私には生き別れの姉がいた。青年は膝の上にちょこん座る少女の頭を撫でながら云う。先ほどまで少女を膝に載せて、お馬さんごっこをしていたためか、額にうっすらと汗をかいている。そうね、お兄様。 青年の膝に向き合うような恰好で座っている十歳前後の少女は青年の顔をあどけなく覗き込んだ。硝子を俵め込んだような瞳に、ゆるやかな漆黒の髪に、白いドレス。白いエナメルの靴を青年の両膝の横でぶらぶらと揺らしている。硬質な美しさを持った少女だった。 姉はとある高名人形師がぜひともモデルにと乞う程、美しい少女だった。姉は幼い頃に神隠しに会い行方知れずになっていた。私の記憶にあるのは、神隠しに遭う前の十歳の頃の姉の姿だけである。医院を経営していた両親は四方八方手を尽くして探したが、姉の行方は一方に解らなかった。当時は商売敵がかどわかしたもの、はたまた姉は美しい少年だったからどこかの国に売り飛ばすために誘拐されたなど、色々な噂があったが、どれも雲を掴むような話だった。 そうね、お兄様。 少女は相槌を打つ。紫色の寄薇の髪飾りを髪に飾り、チョーカーのように首に巻いた細い紫色のリボンをせわしなく弄っていた。 あれは、いつのこととだったか。姉を探すために探偵となった私のところに、あの話が持ち込まれたこから、全ての始まりだった。 青年の回想のハジマリ、ハジマリ。チョコレートひとつ頂戴な。 ある夏の日に奇妙な客が、探偵の事務所に顔を見せたところから幕が上がる。裕福な実家のおかげでお金に困ることのない探偵の事務所は小洒落た三階建てのアパートの一室にあった。奇妙な客は黒衣の美少女と、その執事の姿をしていた。白昼の悪魔がにゃあと言って通りを横切って行く。金魚売りの声。呆れる程に、のどかな昼下がり。 「少女屋と云う娼館をご存知ですか??」 断髪に紡の夏物の白い長橋禅が透ける黒い紬の着物に紅地に黒い花が散っただらり帯を締めた美少女が、小首を傾げながらまるで近所にお茶でも飲みに行くような気軽な感じで探偵に云った。にこやかな無邪気そうな笑みが美少女の唇を彩る。いや、今までの様子ではもしかしたら少女はお茶を飲みにきているだけかもしれない。胸に抱くは、赤い目を包帯でぐるぐる巻きにされた兎の人形。年端が行かないにみえるが、その言動は幼い少女のようには思えない。実は見知らぬ依頼人は事務所に来るなり、執事に命令してお茶を入れさせたからである。ずうずうしい限りである。わざわざ持参するだけあって、西洋菓子と紅茶は確かに美味しかった。どうやら執事のお手製らしい。なかなか器用なものである。探偵が返事を考えあぐねているのを見てとると、美少女の紅い唇が、片端を持ち上げるような奇妙な笑みを浮かべる。だいたい、そもそも未だ年端も行かない少女が口に出すような話題ではない。しかし、赤いベルベットが貼られた安楽椅子に腰掛けてヒトの意地の悪そうな笑みを浮かべた顔からは、冗談を云ったつもりではないことは明白だった。 「ご存知なくて、ご存知なくて。あら、それはまことに残念、無念。少女屋は、オリンピアこと僕が営む中国娼館国の外観に趣を凝らした衣装の数々がお客様を出迎える会員制の高級娼館ですのよ。紅殻格子の吉原とは、また一風変わった気分が味わえること請け合いです。夢と冒険の大暗室。尚、こちらの執事はコッペリウスとでもお呼び下さいな」 探偵の困った様子に、漸くオリンピアと名乗った美少女がにっこりと笑みを浮かべながら言った。そして白魚のような手が、傍らに立っている執事を指差した。指差された執事が、軽くお辞儀をして紹介はお終い。それにしてもオリンピアとコッペリウスとは、さてはて不思議。 「で、実は今困った事が起きていますの」 オリンピアは小首を傾げながら言う。云っておくが、探偵の目には好意的に見てもオリンピアの様子は困ったヒトには見えなかった。探偵は、オリンピアに胡乱な眼差しを向ける。しかし、少女の笑みを崩せそうもなかったのは云うまでもない。 「先日怪奇誘拐王から予告状が参りまして、是非とも探偵様に少女屋まできて戴きたく存じます」 執事がオリンピアの科白の続きを云う。まるで、二人ともト書きを読んでいるかのように現実味がなかった。しかも『怪奇誘拐王』とは、いかにせん。あまりにもくだらない怪盗の名前のが依頼を断ろうとしたところ。探偵が言おうとしている科白を予知でもしたのか、美少女が探偵の断りの言葉をさえぎって云った。 「そう断られるのを見越して、探偵さんのお茶には薬を入れましたの。そろそろ効いてくるはずです。ほほほほほほほ」 少女の高笑いが探偵の事務所に響き渡った。どうやら、どうしても探偵に有無を言わせないつもりらしい。しかしながら、なぜゆえ、そこまでして探偵に固執するのか謎である。何か意味でもあるのだろうか。探偵はわけが解らなった。だんだん痺れる体と、ぐるんぐるんする視界。わざわざお茶を持参したのは、こういう訳であったのか。美少女の高笑いが違う場所から聞こえてくるように感じる。探偵は、気が遠くなりつつ、いったい、自分がどんな事をすればこんな羽目に陥るのだろうと考えていた。災難が、花束を抱えて求婚にでも来たみたいだった。 暗転、暗転、暗転。 夢の中で、姉らしき人物を見かけたような気がした。鬼さん、こちら手のなる方へ。 美しき人形の館へようこそ。 其の二 探偵が少女屋の少女達の部屋を次々案内される事、ならびに怪奇誘拐王の予告状が娼館少女屋に送付された事目隠しされた探偵が連れて来られたオリンピアの少女屋は、本人が言う通りシノワズリ一風の外観の悪夢のように美しい娼館であった。オリンピアの説明によれば、普通の楼館に比べるとかなり毛色の変わった娼館らしい。禿のくらいの年頃の少女達が相手をするらしいが、その少女たちは特殊な育てられ方をしたらしく花魁も顔負けな教養を仕込まれているという話である。秘密の花園と言うところであろうか。一部屋毎、趣を凝らした内装と、しどけない少女達が待ち受けていう。いや、中には少女の格好をした少年もいるらしい。オリンピアは、少女屋につくなり一部屋づつ探偵を丁寧に案内した。どうやら、さすがに本日は休業しているらしい。美しき人形の館。オリンピアが古今東西から集めた少女達。オリンピアによれば、少女達全員に、纏足を施しているとのことである。 『鳥篭娘々』 鉄製の中国風の鳥篭の中に寝台が置かれている。鳥篭の部屋の主は金糸雀と呼ばれる少女。黄色のチャイナドレスに、美しい声で歌いまする。ただし、少女は歌いはすれど、言葉を喋る事はない。 『真珠姫』 青一面の部屋の真申には、真珠貝を模った寝台と小さな西洋風のバスタブ。バスタブの中でゆらゆらしていますは、青いきらきら光る尾びれをつけた人魚姫。こちらも金糸雀に負けず劣らず、美しい歌で聞くものを惑わせる。 『十二夜』 暗闇のカフェに、男装した少女と女装をした少年の双子が座っている。少女は黒いベルベットの三つ揃えに真紅のネクタイ。少年は、鹿鳴館の舞踏会に出るようなバッスルスタイル。蓄音機から流れる音楽に合わせて踊ります。だんす、だんす。 『伽倶耶』 御簾の奥には、十二単を着た少女がひとり。注文の多い少女。天井には、フラスコ画のごとく棚引く雲と赤い満月がゆらめき、部屋中に白い兎の人形と竹林。少女は扇の影に顔を隠し、くすくすと笑う。 『死女の恋』 オフェーリアと呼ばれる少女が船を模した花を散らした寝台に横たわっている。アスラバスターのような肌にふっさりとした睦。白い薄物に、黄色い水仙のブーケを持つ先細りした手。死女と言うだけあって、その体は恐ろしいくらいに冷たい。 さて、屍となっているのは、オフェーリア。船の上で、死んでます。胸には、木の杭。首には鎌を半ば刺され、美しい髪が扇のように広がっている。美しかった瞳はどんより濁り、断末魔の叫びの唇がいと哀れ。杭の刺さった胸の上には、黒いカードが一枚。 はてさて、なぜゆえこんな無残な死を迎えなければならないのか。それは、東洋の謎と神秘なのでございます。 「殺し方が間違っているんですよ」 「殺し方が間違っているのですわ」 屍体を見るなり、執事とオリンピアが口々に言った。 「思わせぶりな名前を部屋につけるから、間違えるんですよ」 執事が厭味っぼく言った。 「確かに、『死女の恋』」と言えば、クラリモンドだけど。間違えるのは解るが、でも一応ちゃんと、オフェーリアと名前を付けているのだぞ。沙翁を読んでいれば解るはずだ」 オリンピアが執事に向かって一所懸命弁解を言い張る。それにしても、何かが間違っている会話である。困ったものである。 「‥・何か間違っていないか、お前ら」 探偵の呆れたような突っ込みにオリンピアと執事が動じた様子はなかった。探偵が思わず頭を抱えたくなった事は言うまでもない。今、ここにいる状況を諦めたからと云って、常識まで捨てるつもりはさらさらなかった。それにしても、この惨状に余り動じない探偵もどうかと思うのは如何なものだろうか。 「劇場型殺人を気取るなら、もう少し勉強するべきです」 オリンピアと執事が探偵の方を向いてが声を揃えてきっぱりと言う。それを見た探偵が、更にふかぶかとため息をつきたくなったのは言うまでもない。何かが違っている、しかし何が違っているのか探偵には、目の前に自信に満ち溢れている二人に指摘する自信がなかった。 「で、これが予告状ですの。この度、麗しき白雪姫を私のコレクションに加えたく候。明日、草木も眠る丑三つ時に戴きに参上したく申し候。怪奇誘拐王拝」 オリンピアが甲高い声で、オフアエーリアが胸に抱いていた黒いカードを読み上げる。 目的が簡潔に書かれたとてもシンプルな文だった。探偵は、オリンピアが未だ『白雪姫』と言う部屋には案内されていないと事を思う。どうやら、オリンピアは美味しいものは最後まで取って置く性質なのだろうと探偵はなんとなく思った。 「‥・て、事は。何だ、この女の子を殺した奴は、白雪姫とやらをコレクションに加える予告状を置いてくために、わざわざ殺したって言うのか」 探偵は今にもオリンピアに殴りかかって行きそうな顔をする。余りにも意味のない死に眩卓さえ感じる。その殺気だった姿は、喧嘩上等のうたい文句に恥じないものであった。 「そうだと思います」 オリンピアの能天気な答えに、探偵は呆れて声も出なかった。普通、予告状を置いてくだけのために、少女をひとり殺していくことはないだろう。さすがの探偵にも、到底理解できないことだった。そういえば、何故ひと一人死んでいるにも関わらず、オリンピアは官憲を呼ぼうとしないのだろうか。官憲が呼べないような後ろ暗いことでもあるのだろうか。いや、後ろ暗い事が沢山ありそうである。 其の三 探偵が白雪姫に心奪われる事、ならびに怪奇誘拐王が少女屋に予告通りに現れる事。『白雪姫』昼なお暗い部屋の中央には、蓄薇が巻きついた黒い柩。真紅の内張りをされた柩の中には血色が失せた白いドレスを着た女王然としたひときわ美しい少女がこんこんと死んだように眠っている。漆黒の髪に、濡れたように赤い唇。夜になれば、少女は目覚めるのか。 探偵は、新鮮な空気を吸いに行くと言ってオリンピアと執事を残し、部屋を後にした。扉を閉める寸前に、部屋の中に黒子が沢山現れて部屋の掃除をし始めているようにみえたのは探偵の見間違いであろうか。まるで、不思議の国でも迷い込んだかのようだった。白兎はどこに行ったのだろう。それから数分後、探偵は期待の応えるかのように見事に少女屋の中で迷子になった。オリンピアによれば何度も訪れた客でさえ、紅白の着物を着た禿に案内されなければ部屋に辿りつけない程迷宮のように入り組んだ館とのことだから、それもいた敦し方ないだろう。それだけでも迷子になったのは彼の責任とはいえない。しび上まさか、図ったかのように館の中で笑う大石に追いかけられるとはよもや誰も息うまい。 そして、探偵はひとつの部屋に紛れ込んでしまった。その部屋には『白雪姫』と書かれたプレートが掛けられていたが、次々起きる怪異に神経が鈍化していた探偵が気が付かなかった事は言うまでもない。 部屋の中には、薔薇で覆われた黒い梅が鎮座している。枢の上面は透明な硝子で出来ており、蔓を模った金属製のレリーフの間から中が見えるようになっていた。柩の中には赤い薔薇が敷きつめられ、その中央に人形のような少女が死んだように寝ていた。 探偵は、恐る恐る柩に寄った。美しい寝顔を見せる少女が一人。血のように紅い襟、雪のように真っ白い振袖。血のように紅い伊達襟に、白雪の刺繍がされた黒い鈴子の帯を締め、長い髪には大きな白い薔薇の髪飾りをしている。 美しい少女人形。 少女は探偵の姉とよく似た面差しをしていた。堕ちていくような眩章と、胸の内で広がる甘酸っぱさ。まるで、幼い少年が初恋でもするような感じであった。眠れる少女嬉婦に探偵は心奪われてしまったらしい。 「お早いですね」 探偵の感慨を破る声。見れば、扉のところにはオリンピアと執事。オリンピアは室内にも関わらず、白い日傘を蓮っ葉にさし、執事は大きなバスケットを持っている。そして、二人ともチシャ猫のようなにやにや笑いを顔に貼り付けていた。いったい、いつからいるのだろう。少なくとも探偵は全く気が付かなかった。 「お早いとは、何だって??」 探偵は少々憮然とした顔になる。口調も相乗効果で怖いものになる。いいところが彼女らの登場で台無しになったかのような、どこか割り切れない気持ちがした。これを通常、八つ当たりと云う。しかし、オリンピアは、町中のチンピラが怖がったと言う探偵のにらみにも一向に応えた様子がなかった。おそらく、かなり面の皮が厚いに違いない。 「あら、ご存知でこの部屋にいらっしゃったのではなくって。その子が、例の白雪姫ですのよ」 オリンピアは、小首を傾げ、白い扇を帯から引き抜くと口元を隠して声を立てて笑った。その笑い声に隠された奇妙な響きに探偵は後になるまで気づくことはなかった。オリンピアの科白に、探偵はぎょっとして柩の少女を見直す。恋してやまない、いなくなった姉に似た少女が怪奇誘拐王の毒牙にかからんとしている。勿論、探偵が俄然やる気になったのは云うまでもない。人間、目の前にぶらさがる人参は大切である。でないと、ない袖は振れない。 白雪姫は、眠り姫。踊り子さんには、触れてはいけません。オリンピアの話によると、白雪姫は少女屋に運ばれた時から一度も目を覚ましたことがないらしい。その結果、眠ったままの白雪姫は誰も手に入れたことがないと云う事である。それだけではなく、少女屋の少女達はみな大夫並みのえり好みをするらしい。落語の『五人廻し』も顔負け、なんのそのである。 「もしかしたら、誰かを待っているのかもしれませんね」 オリンピアは、そう話を締め括った。それでは、お茶の時間に致しましょう。 オリンピアは執事に命じて、白雪姫の部屋にテーブルと椅子を用意させると。用意させたテーブルにピクニックでも始めるかのように、バスケットの中からお茶やサンドイッチやら、洒落たプチフールやら、珈琲に紅茶を魔法のよう取り出して並べた。どうやら、オリンピアと執事も怪奇誘拐王を白雪姫の部屋で待つつもりらしい。やはり、どう好意的に見ても余り困っているようには思えない。 「さて、怪奇誘拐王の予告した日時は今夜十二時、あと一時間程度ですね」 オリンピアは懐から懐中時計を取り出して、針の位置を確かめる。その時だった。 「やあ、お待ちどうさま。僕が怪奇誘拐王さ」 青い燕尾服にシルクハットと、そして裏地が目に染みる赤地の黒いマント姿の怪奇誘拐王の登場。ご丁寧に顔を隠すためなのか、マスクをしている。絵に措いたような怪奇紳士姿であった。明るく健全な登場の仕方だった。あまりにも正攻法すぎる。 「時間が間違ってるじゃないか、早すぎるぞ」 探偵が慌てまくりながら、思わず怪奇誘拐王に苦情を言う。確かに、予告時間前に怪奇に来られても、心の準備が出来ないだろう。怪奇誘拐王はきょとんする。そして、懐から懐中時計を取り出して時間を確かめたかと思うと、明るく自分の後頭部を小気味良く叩いた。 「やや、しまった。僕としたことが時計の螺子を巻き忘れていた。どうやら、昨日の十二時から止まっているようだね。なあんて、お茶目な僕」 「その前に気づくような気がするんだが・・・」 あまりの誘拐王のお間抜けさに探偵は目が点になった。普通の感覚ならば当然の対応だろう。しかし、この怪奇誘拐王を名乗る人物も余りその毒のある台詞に困った様子はない。どうやら探偵以外の登場人物は、神経がダイアモンドか何かで出来ているらしい。それどころか、怪奇誘拐王はひとさし指を左右に振って、探偵にこう言った。 「ノンノン。探偵さん。この位の番狂わせにはついてこないと、時代に乗りおくれますよ」 はっきりと言って、全然意味が通っていなかった。 「・‥何故、私が探偵だと知ってるんだ」 探偵の地を這うようなおどろしい声。探偵はそれまでの自尊薇姫とのシリアスなシーンを次々と邪魔をされ、その場に夕食の載った卓祇台でもあったろうものならば、今にも『必殺卓祇台返し』を実行しそうな様子だった。この場に、焼き魚や味噌汁等の古式ゆかしい夕食の載った卓祇台がないことが返す返すも惜しまれる。 「言い忘れておりましたわ。そういえば、予告状のお返事に、探偵さんもお呼びしてお待ちしておりますと出しましたの。やはり、怪盗さんのお相手に探偵さんを用意するのは予告状を戴いた者の義務ですわ」 オリンピアがはっきりきっぱりと言い切った。その昔、天動説を唱えていたヒトの自信にも負けずとも劣らないとも思われる見事な言い切り方だった。 「お前ら、あほか~。どこの世界に、怪盗と文通をする被害者がいるんだ~」 探偵の悲痛な叫び。しかし、オリンピアはそんな探偵の様子を見なかった事にしたらしい。にっこりと笑って、言った。 「ここにいますけど。はい、折角ですので、お茶の用意もしてお待ちしておりましたのよ」 何かが間違っている。間違っているに違いない。その時、何が切れるような音がした。言うまでもなく、探偵の神経である。 「あのなあ~、おまえ等ふざけんのもいいかげんにしろよっ」 探偵はぶち切れた状態で、部屋中に響き渡るような声で喚いた。いや、このような場では喚くしか仕方がなかった。やはり、主人公たるもの目立たなければならない。苦心のワザであった。そして、壁に飾られていた斧やら、サーベルやらを滅茶苦茶に振り回した。しかし、怪奇誘拐王も負けてはいない、懐からボールのようなものを取り出すと、床に投げつけた。床に転がったボールの裂け目から、白い煙が立ち昇る。どうやら、煙幕らしい。たちまち、白雪姫の部屋の中は真っ白くなる。 さて、探偵の明日はどっちだ。 其の四 怪奇誘拐王の快刀乱麻の大活躍をする事、ならびに探偵の恋の行方の事。探偵が気が付くと、いつのまにか、軽々と棺を小脇に抱えた怪奇誘拐王が窓辺に立っていた。マントが誇らしげに風になびいていた。どうやら、煙幕が晴れたのは、怪奇誘拐王が窓を開けたからのようである。あの、真っ白な煙の中で怪奇誘拐王はまんまと白雪姫が入った棺を手にいれたわけである。ふざけた敵ながら天晴れと一言、言ってあげたいくらいである。「さて、みなさん。どさくさに紛れてお忘れのようですが、私こと誘拐王は白雪姫を頂戴しにきたのです。そして、ここに自著薇姫を戴いた事をここに宣言致します。領収書もここに用意してありますので、あとはよしなに。それではみなさんご機嫌よう」 「看板に偽りありだ、いつどこで大活躍したんだ」 探偵は、余程納得が行かないらしく、あらぬ方向に向かって苦情を申し立てる。確かに、気が付いたら話がどんどん進んでいたと言うのは、主人公としてはやりきれないだろう。これこそ、転がる石の如くである。 「それはね、探偵くん。我輩は、章と章の間に大活躍をしたのだ。それでは、みなのもの、さらばだ、アデュゥー」 必殺投げキッス。窓の外にはやはりいつのまにやらショッキングピンクの色をした気球が停泊して誘拐王を待っていた。気球の中には、誘拐王と同じ顔したその他三名が乗っていた。どうやら誘拐王は四つ子らしい。気の狂ったような気球には『怪奇誘拐王』と住所らしき町名番地が染め抜かれている。たぶん、彼の持ち物には、全て名前と住所が書いてあるに違いない。誘拐王は棺を小脇に抱えて、ひらり気球に乗った。 最後までケレンみを忘れないお茶目な怪奇誘拐王だった。 怪奇誘拐王まんまと逃げる。しかし、そうは問屋が卸さなかった。ふと、探偵はオリンピアが非常に楽しげな表情をしている事に気が付いた、しかも数を数えるかのように指を折っている。 3・2・1。 眩い閃光が空に走った。突然、怪奇誘拐王が乗った気球が爆発したのである。燃えながら落ちて行く気球。探偵が呆然と見ている前で、気球の残骸が少女屋の前庭に叩きつけられた。そして、暫くすると火の中から四人乗りの自転車に乗った怪奇誘拐王とその他名乗る暇なく退場する羽目になった三名が現れ「覚えていらっしゃい」の捨て台詞とともに、街角を曲がっていずことなく消え去った。それにしても、なかなか頑丈な御仁達である。 怪奇誘拐王の華やかなる退場。 あまりの展開の早さに探偵は動けず、真っ白になった。悪い夢でも見ているかのようだった。しかし、ふと我に返ればあの燃え盛る気球の中に白雪姫がいるかと思うと部屋からいても立ってもいられず、部屋を飛び出そうとする。その探偵をオリンピアが呼び止めた。しかし、探偵は止まらない。そこを執事がすかさず探偵の後頭部をはりせんで引っぱたいた。哀れなりけり、探偵。 黒い小悪魔のような少女は、痛いにのたうち廻っている探偵に向かって薄笑いを浮かべて言った。それにしても、非情な輩である。 「あの棺は偽物でしたのよ」 オリンピアが平然と言った。オリンピアが目で合図すると、執事が呼び鈴を鳴らした。どこからともなく現れる黒子。黒子は先ほど怪奇誘拐王が持ち去ったのと同じ棺を捧げ持っていた。そして、白雪姫の部屋は全て元通り。 「それでは、お礼に貴方に白雪姫を差し上げましょう」 オリンピアはくるりと振り返ると、探偵に告げた。もしかしたら、今までの事は悪ふざけしすぎた余興にも思えなくもない。しかし、そんなことをして、はてさてオリンピアに何の得があろう。 「白雪姫が望んだ事ですので、お気になさらずに。それでは、ごきげんよう」 オリンピアは、不思議な事を言って執事と黒子を従えて白雪姫の部屋から出て行った。探偵は呆然とその場に立ち尽くした。何故、どうすればこのような展開になるのか探偵は全く皆目つかなかった。 オリンピアと執事の退場。扉の閉まる音が厳かに聞こえた。 そして、誰もいなくなった。 気が付くと少女がいつもまにか窓辺に立っていた。真紅の瞳が探偵を見返す。真紅に瞳に魔力でもあったのだろうか、探偵は身動きができない。そして、ゆっくりと上半身を起こすと、にっこりわらって探偵に手を伸ばした。操り人形のようにふらふらと動く体。探偵が、少女がじつは人形だと気が付いたのは、首筋に異様に尖った歯を付き立てられる寸前だった。その昔、人形師が作った姉の生き人形。針を突き刺したような痛みが首筋に感じ、つぎに来るは歓喜の悲鳴を上げ続けた。暗転、暗転、暗転。 窓辺で、黒猫がにゃあと鳴いて去った。そして、残るは龍の鳥。 あれは、どのくらい前で、どのくらい昔で、どこで起こった事なのだろうか。そして、ここは一体どこなのだろうか。夢か現か、それとも夜の幻か。青年は一人ごちる。半分夢うつつの中で時間だけが過ぎていく。 青年は、昔からこの生活をしていたかのように感じ、少女屋までもが幻だったかのように感じるのである。そして、白雪姫がにっこりと笑いながら優しく言う。 「それで、お姉さまはどうしたの?」 少女の無邪気な問いかけに青年は思い出す。ああ、そういえば「姉」は、幼いころ私が吸血鬼のような黒いマントの紳士に、珍しいお菓子と取替えてしまったのだと。私は、見知らぬ紳士の「是非、一度会ってみたい」と言う言葉に素直に従ってしまったのだ。珍しい異国のお菓子を貰い、自慢の姉を図らずも売り渡してしまったのである。私はただ、愛しの姉を見せびらかしたかっただけなのに。覚えているのは、紳士が付けた姉の首筋の傷と、紳士につれさらわれた姉の姿。今頃、姉はどうしているのだろうか。いや、この少女が姉なのかもしれない。ああ、これでお姉さまと一緒になるのだ、お姉さまと、お船の上に花を散らして赤い紐で手首を結わいて死にましょう。お姉さまは、『少女屋』でこのときを待っていたのに違いない。青年は、そのことを考えてくつくつと笑った。 暗転、暗転、暗転。 (終幕) |


|
|
|
|
Copyright (C) 2006. Mangougasa. All Rights Reserved. |