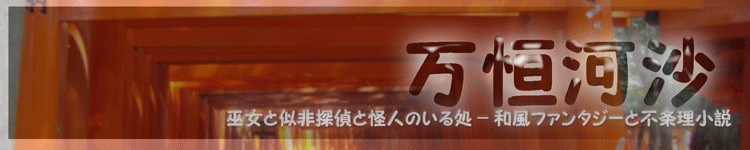
|
| ご案内 | オフライン | さかきちか創作部屋 | ツカノアラシ創作部屋 | LINK | 管理人日記 |
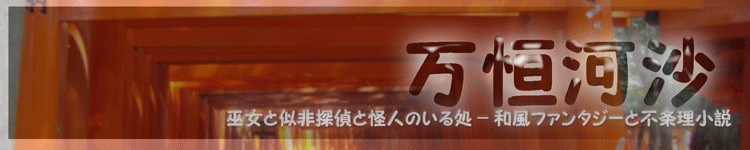
|
| ご案内 | オフライン | さかきちか創作部屋 | ツカノアラシ創作部屋 | LINK | 管理人日記 |
|
ひとくいのかがみ深夜に私の家に訪れた謎の配達人は下を向いたまま、無言でななしの差出人からの贈り物を差し出した。 ななしの差出人から贈り物がきた。その日は非常に疲れていて、いつになく恐ろしく寝ぼけていた。いつもならば差出人を確かめてから荷物を解くのに、その時に限って何故か差出人を確認せずに開けてしまうと言う間違いまで犯してしまう。大きくて平たい桐で作られた箱の中からは、鏡が一枚現れた。鏡の縁に苦悶するような化け物のレリーフが彫られた鏡は、底意地の悪いくらい不気味だった。あまりに不気味なので、そういう事に詳しい友人の聖玲のところへ持って行くことにした。 ここは、『清廉潔白探偵事務所』。警視庁猟奇課警部である凡庸、甘党、被害妄想と三拍子揃った神田川一生氏は、早朝から煉瓦造りのレトロな5階建てのビルの5階の銀色のペンキで『清廉潔白探偵事務所』書かれた硝子が嵌った木製の扉の前に大きな包みを持って立っていた。扉を開けると、神田川をこれまた古色蒼然としたビルに相応しい古風なお仕着せを着た村雨と松風と言う名前の美人メイドさんがぎこちない笑みを浮かべながら出迎えてくれる。彼女らは恐るべき美女ではあるが、異常に顔色が悪く少し無表情なのが難であった。 神田川は、通常の依頼人は滅多には通される事はない探偵のご自慢の図書室に二人の女中さんの先導で案内される。そして神田川は一見すると人のよさそうな優男に見える性悪執事が用意したお茶とお菓子を戴きながら、ここの主である探偵のお出ましを待っていた。探偵は、朝が滅法弱いのである。もしかして、真夜中に散歩でもしているのだろうか。しかし、朝が弱く身の回りの世話を焼く者がいなければ日常生活が送れないほど生活能力に欠ける探偵なんて、あまり実社会では役に立たないような気がするのは気のせいだろうか。因みに、ここの探偵は正体不明ではあるが、優雅に生活できるだけの資産があるらしく、気に入った猟奇怪奇な依頼しか受け付けてくれないと言う注文の多い困ったさんである。神田川は森の中で迷子になったことから、この人物と知り合いになり、現在に至っていた。 出会いは誰も行かないような森の中の牢獄のような屋敷。 そして、書斎の主の聖玲のご登場。男物の黒い和服に羽織を羽織った華奢で小柄な姿が螺旋階段の上に現れた。烏の濡れ羽色の黒髪の下から覗く吊り気味の杏型の大きな目に、ぽってりとした紅を差したかのように朱い唇。まるで人形のような端整な顔を持つ探偵は階段の上から神田川を見て花がほころぶようににっこりと笑った。どうやら、今日は『少年探偵』らしい。探偵は、執事の趣味で、ある時は『少女探偵』だったり、またある時は『少年探偵』だったりする。神田川は、未だにこの人物の正確な年齢と性別を知らない。ただし、本人が言うにはこんな事をするのには理由があるそうだが、如何せん言っている人物が非常に信用ならない人物なだけにまともな理由ではあるまいとは神田川はにらんでいる。おそらくたぶん、神田川は間違っていないだろう。 そして、その慇懃無礼な態度と少々性質の悪い性格から周囲から小悪魔と称される探偵はその可憐な姿に似つかわしくない、ラヴェルのボレロ終結部が流れてきそうな位に威風堂々な態度で、背後に畏まった執事を従えて優雅な動作で階段を下りてきた。これで、両側から悪魔がファンファーレでも鳴らせば、ゴシックなホラーの舞台装置としては完璧だろう。 探偵は図書室の自分の椅子に座ると、今すぐにでもどこかの舞台にに出演することができそうな位に完璧な執事がスクランブルエッグとベーコンが載った皿と、紅茶とクロワッサンをマホガニー製の机に置く。どうやら、探偵の朝食らしい。非常に優雅な生活で羨ましい限りである。 「それで何で、そんな鏡を持っているんですか」 神田川の手元を玲は片眉を引き上げ目を細めいかにも胡散臭い表情をしながら見た。胡散臭げな表情ではあるが、頬に手を沿え唇には面白そうな笑みを浮かべている。どことなく、非常に楽しそうだった。神田川の手元には、人の頭程の大きさの鏡がある。鏡は縁に苦悶したガーゴイルを彫ったような凝った飾りがついていて、いかにも玲が好きそうな物であった。 「昨日の夜、見知らぬななしの差出人から贈られてきた。何か見えるのか、君」 神田川は恐る恐る尋ねた。玲は人には見えない何かが見えると言う話である。一体全体、鏡に何を見たのだろうか。その実、神田川はあまり聞きたくはないのだが、ここで聞いて置かないと後で後悔しそうだった。多分、いや絶対に死ぬほど後悔するだろう。 「うーん、警部。ソレ飾るのは、警部の勝手ですけど。たぶん、喰われますよ」 玲は花が綻ぶかのような笑みをその端整な顔に浮かべて言った。右手で持った金地に薄紫色の藤が描かれた扇で鏡を指し示す。見た者をうっとりさせずにいられない笑みとは裏腹な物騒な台詞だった。神田川は玲の台詞に首をきっかり45度傾げて少し慄きながら問い返す。口の端がぴくぴくと軽く痙攣していたのは、言うまでもない。 「く、喰われる??」 「そう、喰われますよ。まぁ、命がけで美人のお化けと快楽の限りを尽くして寝たいっていうなら僕は止めやしませんけど。体が持つのは五日間位かな。ねぇ、巽」 玲は口元を扇で隠しながら、椅子にかじりつきながら慄いている神田川を面白そうに見ながら傍らに畏まって控える性悪執事巽に同意を求めた。くすくすと唇から漏れる笑い声。神田川の反応と鏡が楽しくて仕方ないらしい。困ったものである。 「玲様の仰る通りかと存じます。神田川様、五日間お楽しみになれば、残りの人生お捨てになさると言う事でございましたら鏡を飾られるとよろしいかと」 白い背広を着た人の良さそうに見える優男がおっとりとした口調で主人に同意する。一見すると彼は口調も表情もとても優しげに見えるが何気に更に酷い事を言っているような気もしないでもない。本当に血も涙もない人たちである。神田川の口から乾いた笑いが空しく漏れた。自分を哀れみたくなる位、おもちゃにされている気分である。 「たぶん、楽しめるのは初日か二日目くらいじゃないか。あとは衰弱する一方だし」 「蟷螂が一度の逢瀬で頭からバリバリと食べられてしまう事を考えると幾分マシかもしれませんよ」 主従はにこにこ笑いながら更に神田川に畳み掛ける。ただし、全くと言って良いほど神田川を心配するような台詞は出てこなかった。しかもどこかピントのズレた台詞である。示し合わせたかのように困った主従であった。まぁ、だいたい今までの台詞を見ればこの二人にまともな対応を求める方が間違っているに違いない。 「……何気に二人とも酷い事言ってないか、ソレ。しかもにこにこ笑って言う台詞じゃないぞ」 神田川も何か理不尽さを感じたらしい。一応、主従に向かって指差ししながら指摘をしてみる。これを無駄な抵抗と言う。玲は神田川のせめての攻撃にも笑みを崩す事なく、更に眉を思わせぶりに上に引き上げた。何か悪い事でも企んでいるかのような表情だった。それを見て神田川はため息をつく。絶対、探偵は何か悪いことでも考えているのだろう。神田川は、何故玲は探偵を職業として選ぶのではなく、素直に秘密結社の首領等の悪役でもやっていてくれないのだろうと天を恨んだに違いない。 「そうですか。仕方ないですねぇ。巽、警部さんに見せて差し上げろ」 玲は目を細め、わざとらしく扇で口元を隠して嘆息しながら巽に指示を与える。扇で隠している唇の端が幾分気持ち吊り上っていた。仕方ないと言うより、何か悪い事を思いついたような表情である。哀れなりけり、神田川。そもそも、はじめから相談相手の選択が間違ってような気がしないでもない。 「畏まりました、仰せままに」 巽は玲の言葉に軽く一礼すると都合良く机の上に置かれていた黒皮手袋をはめて神田川の持っていたいた鏡を取り上げ、おもむろに鏡の中に手を突っ込んだ。目を点にさせた神田川の目の前で巽の腕は肘の辺りまで鏡の中に飲み込まれている。そして、何やら巽は中で掴んだらしく、表情も変えずにその何かを引き上げた。 ずるっと鏡から引き上げられたのは、両腕の無い女の上半身。下半身は蛇のように長くなっているらしく、未だに鏡の中。巽は顔色ひとつ変えずに女の首の辺りを掴んで引き上げていた。ぬらぬらと濡れるように紅い唇に、ぬばたまような黒髪。女は紅い唇から、声にならない叫び声をあげている。女は巽の手から逃れようと躯をしきりに捩るが、巽の手は万力のようにびくともしない。こんな優男のどこからそんな力が出るのだろうか。謎である。因みに、神田川は女が鏡から現れた途端うわっと情けない悲鳴をあげると、すぐさま玲の背後に隠れてしまう。小心者の名に恥じない行動である。おかしな目には、玲と知り合ってから良く会うが未だに慣れない神田川であった。 「如何致しましょうか、玲様」 巽はにっこりと主人に笑いかけながら言う。正体不明の気味の悪い物体を捕まえているとは思えないぐらい爽やかな優しげな笑みだった。その昔、数多くの女性が騙されたらしいと噂されるだけある。できることなら、ぜひ後ろからとび蹴りを食らわせたい位に爽やかな笑顔であった。嘘くさい事この上なしである。 「好きにすれば」 「左様でございますか」 と、巽は答えると、女の首を左手で掴んだまま右手で女の顎を持ち上げて接吻した。神田川の顎が落ちる音がする。女は巽の唇から逃れようと厭々をするように首を振ろうとするが無駄な抵抗に終わる。その内、女がうっとりしたように唇を受け入れはじめた。びくびくと蠢く背中。それと同時に女の髪から色が抜けていき、艶やかだった黒髪が白髪と成り果てる。髪だけではなく、顔には皺がより、皮膚の弾力が失せていっている。女も自分の異変に気がついたのか巽から逃れようとするが、時すでに遅し。女の躯は白くひび割れ、割れた石膏像のように崩れ落ちてしまった。同様に、鏡も見る見るうちに白茶けたかと思うと砂のように崩れたのである。残ったのは、床に広がる白い砂。床の掃除が大変そうである。 「お前ねぇ。好きにしろと言ったけど、喰ってしまう事はなかろう」 玲は扇で口の辺りを隠したまま呆れたように小さく嘆息すると、片眉を引き上げワザとらしくちろりと巽を横目で見た。扇で隠された口元には先ほどとは少し違う微かな笑み。巽に行為にそんなに呆れている訳ではないらしい。巽は手袋外しハンカチで口元を拭い、薄く爽やかな笑みを浮かべた。 「人前でご婦人と接吻する程度で動じる程、初心ではございませんので」 と、言って巽は更に笑みを深くしたのである。そういう問題だろうか。何か何処かが違っているような気がする。そもそも正体不明の化け物をご婦人の範疇に入れてよいのだろうか。その上、会話が微妙に噛みあっていないような気もする。因みに、可哀想な神田川くんはすっかり石化して、元に戻るのに暫く掛かったそうである。 しんちゅうあそび久しぶりに事務所に顔を出すと、事務所を任せきりになっている腐れ縁の所員から小言に近い厭味と近くの川に変わって屍体が上がったと言う話を聞いた。私はそれほど興味がなかったが、飼っている『少女』が見に行きたいとしきりに可愛い声でねだるので仕方なく散歩てがら見物に行く。黒檀のように黒くて長い髪、血のように紅い唇に雪のように白い肌。銀糸で刺繍された白い振袖を着、黒い帯を締めたまるでお人形のような『少女』を横抱きにし、上体を起こしたまま両腕を私の首に巻き付かせる。ぽっくりを履いた足がぶらぶらと揺れた。『少女』は一人で歩けないわけではないが、小鳥を鳥篭に閉じ込めてしまうように屋敷に閉じ込めて滅多にこちらに出てはこないので、外が物珍しいのか逃げ出すワケではないが眼を離すとすぐに一人で何処かに行ってしまう。そして、何処かへ行ってしまって、私が探して迎えに行くのをにこにこと笑いながら待っているのだ。 橋の下の川面に浮かぶは男の屍体。 ゆらゆらと水面には、左手に赤い紐を結んだ男の屍体が浮かんでいる。男の左手に結ばれた赤い紐の先には誰もいない。ひとりきり。水面に見え隠れする男の顔に浮かぶは、うっとりとした笑み。ひとり心中。この街の住人は余り積極的に官憲と関わりたいと思っている者が少ないため未だ放置されているのだろう。ゆらゆらゆら。男の屍体は水面が揺れるのに合わせてゆらゆらと揺れていた。 男の屍体を二人で暫く見ていると『少女』が私の背広の襟を軽く引くと、橋の袂の柳の方を指差した。『少女』はにこにこと楽しそうな笑みを浮かべている。『少女』が指差した先には、藍と白の市松模様の着物を粋に着た美しい女が立っていた。目の下の黒子が色っぽい。女は私が女を見ている事に気がつくとトロリした笑みを浮かべる。男心を擽るような非常に魅惑的な笑み。女はゆっくりと私達に近づくとと、媚びるような下目使いでセンセと私の事を呼ぶと私の腕に触った。因みに私は自他共に認める女にだらしないタチだが、残念ながら私と彼女は知り合いではない。 「センセもアレを見てるんですね」 女は私の腕を放し橋の欄干に膝をついて凭れかかりながら橋の下の男の屍体を指差して、ほくそ笑む。にぃっと、女の唇の両端が引き攣るような三日月のような笑み。女は屍体の男に悪意でもあるかのような笑みを浮かべていた。私は女の隣に行き、同じく橋の下を眺めなら女に尋ねた。 「随分と見ていたようだけど、姐さんの知っている奴かい」 「いやね、馴染みの客に良く似ているんですよ、あの屍体。あら、随分と可愛らしいお嬢ちゃんね。センセのお子さん」 女は首を振ると、ここで初めて『少女』に気がついたような顔をして私に尋ねた。『少女』と私が親子に見えないのは解りきっているが、答えるのは面倒くさい。さて、どうしようかと考えて私が答える前に『少女』が口を開く。 「コレは家来」 『少女』は私を指差しながら女に向かって可愛らしい声で抗議した。可愛らしい声だが、『少女』の口調や立ち振る舞いは妙に威厳を持っている。私は空いている手で顔を半分隠しながら、少し天を仰ぎ「あああ」と溜息のような声をあげた。確かに間違っていなが、物は言いようと言うものがある。そう、あの時から私たちはずっと主従ごっこをしている。主が『少女』で、私は『家来』。 女は一瞬、戸惑った顔をすぐに冗談だと思ったらしい。女は目尻に涙を浮かべ口に手を当て、大仰な動作で笑い出す。躯を二つ折りにし腹をよじって笑う女の姿。女は目尻に浮かんだ涙を拭いながら身を起こした。そして、女は『少女』に向かって揶揄かっちゃ駄目よと言う。『少女』は女の言葉に珍しく、頬を膨らませ口を尖らせて怒ったような表情をする。可愛らしい表情。しかし、『少女』は更に何か辛辣な事を女に言おうとしたので、『少女』の可愛い口を空いている手で塞いだ。『少女』は抵抗してに私の指に噛み付くが、掌でした口の蓋は外さない。そうでもしないと、『少女』は女が先程笑った事を死ぬほど後悔した挙句に川に身を投げてしまうような事をするに違いない。勿論、私個人としてはそうしても構わないが、ここは大人しくして貰った方が得策のような気がする。 「この子の言う事は気にしないで下さい。それにしても、他人の空似の割には凄く嬉しそうな顔をしてるじゃないか」 「嬉しそうに見えますか」 「嬉しそうに見えるね」 「あの屍体の男が遠い昔に私を裏切った男に似ているからでしょう」 女は着物の袖で口元を隠しながら、くすくすと声を立てて嗤った。気のふれたような厭な嗤い方。私は女の言葉に下手な事を言って、薮蛇にならないように気のない曖昧な相槌をついて言った。 「だから、殺したのか」 「はい、だから殺しました。一緒に死にましょうと誘って死へと誘いました。何が悪かったでしょうか」 私の問いに女はくすくす笑いを止めて能面の泥眼のような顔でにたりと嗤ったのである。 「いいや、私には関係ないし、好奇心が満たされた今じゃ興味もないね」 私は取り付く島もないような口調で女に言って、事務所に戻ろうと女にくるりと背を向けた。『少女』が私の腕の中で聞き分けなく未だじたばたと何かしたそうに暴れているが無視をして押さえ込む。少女はいざ知らず、私はすでにすっかり興味を失っていた。 「センセ、お名前は?」 女の問いかける声。ねっとりと躯に纏わりつくような媚びた口調で女は私に問いかける。 「残念ながら、私はそこの男の二の舞になる気はないね」 私は立ち止まって振り返り、腐れ縁の事務所所員から『女殺し』と揶揄される笑顔を浮かべて女に向かって言ったのだった。女は恨めしげな顔をすると、低い声で「ひとでなし」と言い陽炎のようについっと消えた。今までそこにいたのが嘘だったのかように女は消えたのだった。私達はその光景に驚きもせずに事務所に帰ったのだった。これ位で驚いていては、ここでは暮らしていけない。 あれから年月が流れ、元々ある事務所とは別に設えた事務所で私が紅茶を淹れていると腐れ縁の所員の鬼堂篁が朝帰り姿のまま事務所の奥の書斎にやって来た。篁は首の辺りをしきりに揉みながら、近所の川に赤い紐で片手を括った男の屍体が上がった事を世間話として話す。あそこにゃ、定期的にそういう屍体があがるんだよななどと言いながら篁は背広の上着をソファ投げかけてだらしなく座り込んだ。彼女の行儀の悪さに私が軽く睨むと、彼女は頬をひくつかせながら「いーじゃないか」と言いながら目線を逸らす。篁の言葉に今まで大人しく読書をされていた玲様が頁を捲る手を止め机に膝をつき掌に顎を乗せた姿勢で顔をお上げになる。玲様は面白そうな顔をされていた。 「ああ、あのお姉さま。まだやってるんだ」 玲様はそう言って、私を横目で見ながら口元を扇で隠して声を立てて楽しげにお笑いになったのだった。知っているなら、止めてやればいーじゃんと言う篁の言葉は黙殺する事にする。それにしても、恐るべきは女の執念深さである。あれならば、いつか橋姫でも何にでもなれるに違いない。私は二人に気づかれないように、深々と溜息をついたのだった。 |


|
|
|
|
Copyright (C) 2006. Mangougasa. All Rights Reserved. |