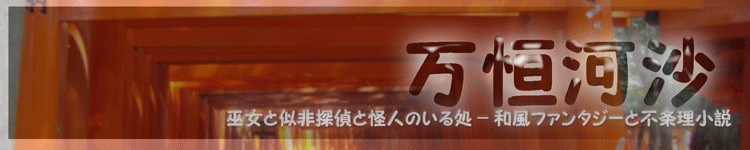
|
| ご案内 | オフライン | さかきちか創作部屋 | ツカノアラシ創作部屋 | LINK | 管理人日記 |
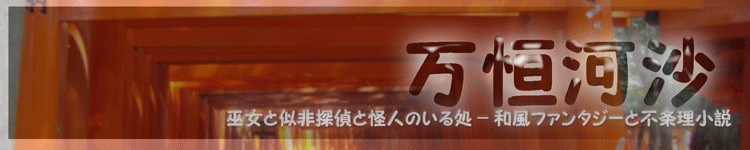
|
| ご案内 | オフライン | さかきちか創作部屋 | ツカノアラシ創作部屋 | LINK | 管理人日記 |
|
バーの外で待ち合わせ肉体のかせから離れて、夜歩く。首から血をしたらせて、くるりくるりと踊るかのように歩く。薔薇の葬列。青白い首からしたたる血は薔薇のように、私たちの白いドレスのような衣装を彩る。くるり、くるり。私たちは円舞を踊る。私たちの胸の中にあるのは、恐怖。すでに、あの男からは逃れているいると言うのに、逃れられぬ恐怖。私たちは黒い森の中心でくるり、くるりと踊るかのように歩いている。その数は次々に増殖し、永遠に増えていくかのような気すらしていた。そんな時、あの男が現れたのだった。 その酒場は、『薔薇の葬列』と言う名前の赤い色をした混合酒が恐ろしいほどに美味しいと評判という話だった。一度、口にすれば最後、虜になる事請け合いと言う噂だった。しかし、そのレシピは門外不出。店主のみが作れる酒だった。 凝った文字で『夜会』と書かれた木の看板が、ランタンの朧げな光の下に、その存在をかろうじて知らしめているひっそりとした店。ちょうど黒い森の奥に位置する隠れ家のような雰囲気を持った店だった。店は髪が白くなりかかっている初老のマスターがひとりで営んでいた。 その日は珍しく店には閑古鳥が鳴いていた。 (カラン、カラン、カラン) 来客を知らせる扉のベルの鈍い金属の音が鳴り響き、本日のお客様のご登場。本日のお客様は、白いレースの襟が付いた黒いワンピースを着た色白の印象的な美少女。額で分けた黒髪から吊り眼がちの杏型の緑色の目が覗いている。少女のご注文は、とろけるほど甘い甘いカシスソーダー。エルキュールーポアロの好物であるクリーム・ドーカシスを炭酸水で割る方法で簡単に作れる飲み物。すぐに、ワインレッドの甘い液体が入ったグラスが少女の目の前に置かれた。水滴をびっしりと身に纏ったグラス。 カラン、カランと氷が硝子に当たってしきりに硬質の音を立てる。少女はグラスに口を付けると、美味しそうに微笑んだ。紅い液体が減っていく。そして、開演のベルが鳴る、 あれ、お嬢さん、おひとりですか。違う?ああ、待ち合わせですか。お連れさんは後でやってくるんですね。それは、良かったですねぇ。え、何か良かったって。おや、知りませんか。大きな声じゃ、言えませんけどね。ここ辺りじゃ、お嬢さんみたいな可愛い方がたびたびいなくなるってことが良くあるんですよ。 悪い冗談を言わないでほしい?いえいえ、冗談なんかじゃないんですよ。実際にあったことなんですよ。たぶん、お嬢さんが小さい頃に起こったことだから、知らないかもしれませんねぇ。十年ほど前でしたかな、この界隈で女性が良くいなくなったんですよ、それも美人ばかり次々と。行方不明になった女性達に、失踪する理由がない上にさしたる共通点もなかったんで、当時はかなり騒がれたんですけどね。本当に知りませんか? おやおや、顔が白いですよ。怖がらせてしまったみたいですね。でも、大丈夫ですよ。もう十年も、前のことですからね。ここ十年間ほど、女性が突如消えていなくなるって話は聞いてませんからね。ここだけの話ですけど、今現在そういうことが何故起きなくなったのかは解らないんですよ。ただ、ある日突然、ぱったりとそういうことが起きなくなっただけというわけでね。これには、いろんな無責任な話かおりましてね。例えば、犯人が死んでしまったとか、犯人が仕事場を移動してしまったとか。ま、ロクでもない話がそりゃあ沢山あるんですよ。 ああ、そうだ。その中でもとっておきの話をお聞かせしましょうか。これが結構気味の悪い話でね、ある探偵が関係しているって話なんですよ。 え、どこが気味が悪い話だって。内容がですよ、内容がね気味が悪いんですよ。俄に信じがたい話なんてすが、どことなく真実味を帯びていて、わたしも初めてその話を聞いた時にはぞっとしましたね。あれほど、不気味で悲惨な結末ってあるものですかねぇ。世の中、理不尽でなかなかままならないものですよ。え、誰にとって不気味で悲惨かって?さて、誰でしょうね。うっふっふ。 それにしても、なかなか、興味が惹かれたでしょ。不気味な夜に、不気味な探偵現わるってね。 かの探偵の名前は青柳竜衛。当時は二十代の後半から、三十にさしかかったくらいの年齢だったらしいですね。この男は噂によると、一見すると優男風で色気のある惚れ惚れするようないい男だったらしいですよ。事務所をこの辺に構えていたそうでね・・・・・・この話の後に消息不明になったらしく、今はいったい、どこで何をしているんだかは解りませんけど。ずいぷんと性悪な男たったそうですからね、きっとロク生活は送ってないんでしょうけど。もしかすると死んでいるかもしれませんねぇ。その方が良いと思いますけど。え、なんか恨みでもあるみたいに聞こますか?やっぱり女性は性悪でいい男が好きなんでしょうかね。同性としてはそんな奴がいたら、ぜひ後ろから飛び蹴りを食らわせてやりたいと思いますけど。そういえばこの男は、女性の方も不自由するような奴じゃなかったらしいですよ。不自由どころか女を泣かせるような奴だったそうですね。救いようのない厭な男ですよね。ぜひ、後ろから飛び蹴りをしたくなったって。ああ、やっぱりそうでしょう。それにしても、なんてそこに女の話が話題に出るかって。まぁ、話を聞いていれば自ずと解りますよ。 この話はその青柳竜衛という男があるバーに現れたところから始まります。バーの名前は解らないのですけれど、話によればなかなか雰囲気の良いバーだったそうです。え、ここみたいにかって?嬉しいですねぇ、そういうことを言われると。実は最近になって、ここに久しぶりに開店したばかりなのでね。え、そうは見えないって?これから、ご贔屓によろしくお願いしますよ。 そのバーは、店主オリジナルの紅い酒がとても美味しいと評判だった。その日は珍しく店には閑古鳥が鳴いていた。まるで、美しい女も紳士的な男も、霧雨にけぶる街からみんな蒸発してしまったかのようだった。静かな夜。終末のラッパが鳴り響いたとしても誰も気がつかなかっただろう。 すべて、嵐の前の静けさだった。 (カラン、カラン、カラン) 扉の開く音に初老のマスターが反応する。扉から現れたのはひとりの若い男。男の黒目がちの切れ長の目がマスターに向けられた。黒い服を着た男は、迷うことなく優雅な仕種でカウンター席につく。そして、男はメニューも見ずに『薔薇の葬列』を注文した。この店に来る客の十人中九人くらいは『薔薇の葬列』を頼むのだから、男の選択の仕方は特別おかしいことでない。マスターは軽く頷くとすぐに『薔薇の葬列』作りだす。 「誰かと待ち合わせですか?」 空いた椅子の上には、贈り物らしい大きな箱。紅いリボンに、メリーゴーランドが印刷された青い包装紙。恋人にでもあげるのだろうか。 「いいえ…ああ、この荷物ですね。これは、家で恐らく大人しく留守番をしている子供へのおみやげ」 男はマスターの早とちりを笑って、隣の席に置かれた華やかな形にリボンが掛けられた荷物を手を置く。確かに良く見てみると、包装紙は子供向けの可愛らしい絵柄がついたものだった。 「お子さんがいらっしゃるんですか」 マスターは平静な顔をして会話を続けたが、内心では首を傾げていた。マスターの見た感じでは、男に妻子がいるとは考えにくかった。男には全く生活感と言うものが感じられないのである。 「いや、いません」 男は簡単に否定した。男のセリフは矛盾している。いったい、それはどういうことなのか。解らない。マスターの顔に、なんとも表現しにくい表情が浮かび上がるが、すぐに消える。これには職業的訓練が物を言った。霧雨の夜のひとりだけの客。 『薔薇の葬列』は美しい女性の血のカクテルの名。 マスターは最後に『薔薇の葬列』の味を良くする秘密の樽を開けて、グラスの中に樽の中の液体を注ぎ込む。これで美味な『薔薇の葬列』のでき上がり。そしてグラスは男の元へと届けられた。 「そういえば、ここの『薔薇の葬列』は、とても美味しいと評判だそうですね」 男はグラスを弄びながらマスターに話しかける。淡々としているが、何か冷たいものを感じさせる口調。そして、口調とお似合いな、どことなく妙な妖しげな目つき。マスターは背筋に冷たいものを感じたが、無理やり笑みを浮かべた。 「ええ、ウチの『薔薇の葬列』を飲むと病み付きになるとお客様はよくおっしゃいます」 そう、客たちはこの店の『薔薇の葬列』を一度味わってしまうと、もう他の店の『薔薇の葬列』には見向きもしなくなってしまう。今まで、何人もの人間が秘密を探ったが未だその謎を解きあかしたものは皆無だった。 「何か、秘訣でもあるんですか」 男は何気ない風を装って尋ねる。マスターは商売敵かも知れないと思う。そう、思って見れば男は何となく水商売風にも見えた。しかし、水商売にしては男は品が有りすぎる。マスターには目の前の男がいったいどんな商売についているのか全く予想もつかない。こんなことは、珍しいことだった。 「まあね。でも、そこは企業秘密ですよ、お客様」 「そうでしょうね」 男のセリフに、マスターは少し撫然とする。男の口調にはなんとなく悪意が秘められているようにマスターには感じられたのだった。慎重に隠された悪意。この男が何を考えてきるのか、彼には皆目つかなかった。解らないことだらけである。 「そういえば、ここ最近、この辺りで女性ばかりが行方不明になる事件が起こっているそうですね。それも、美人ばかり」 なるほど、こちらが目的だったのか。ようやくマスターは納得した。美しい女たちはいったいどこへ行ったのか。巷では、謎が謎をんでいた。しかし、誰ひとりとして正しい答えを見つけたものはまだいない。 「そうらしいですね。まだ、誰一人として見つかってないそうですけど」 「そうでしょうね」 男は何か含むような口調だった。男の厭味な言い方に、マスターは少しむかっとして口調が尖る。 「ずいぷんと、意味深なことをおっしゃいますね」 「ええ、だって僕は彼女たちがいる所を知っていますからね。彼女たちは、普通では見つからないところにいるんですから」 男はさも当然のように言った。まるで、挨拶を交わすような気軽さである。 「本当ですか」 もしかして目の前の男が、女たちを誘拐した張本人が戯れに告白したくなったのかもしれない。男の顔に浮かぶ薄い笑み。見た目はひとの良さそうな優男だが、どこかしらそこの知れない笑み。 「聞きたいですか?」 マスターは思わず頷いていた。そう、好奇心は猫をも殺すのである。 あれは、やっぱりこんな夜でした。 その日、僕は失踪してしまった婚約者を探してほしいという依頼を受けたばかりでした。実は、僕の職業は、私立探偵でしてね。ああ、僕の名前は青柳竜衛って言います。これ、名刺ね。清廉潔白探偵事務所って言うんです。珍しい名前でしょ。ある店の前を通ると、店の前に女が立っていました。名前は知りません。でも若くて、はっとするほど美しい女でしたよ。霧雨の中で傘もささずに濡れそぼっていたのが、なかなか色っぽかったですね。どんな女でしたかって?色白で髪が長く、目が大きくて思わず口説きたくなるほどでしたよ。それで、口説いたかって。いいえ、そんなことはしませんでしたね。なぜなら、その女が僕のほうを上目遣いで恨めしげに睨み付けていたからです。ね、怖いでしょう。それも、僕のほうに身に覚えにある女ならともかく、一応はそのような意味では見知らぬ女でしたからね、その怖さたるや口では説明できないほどでした。そうそう、一応見知らぬ女と言いましたが、正確には彼女は見知らぬ女ではありませんでした。 実は彼女はその日、依頼を受けた失踪した婚約者にどことなく似た女だったのです。ただ、似ているだけで、本人であるかは解りませんけどね。と、言うのも彼女の印象が刻々と違ったものに変化するんですよ。同じ女であるのに違う女。それに、少なくとも本人であるならば、様子がただならないと僕は思いました。だって、そうでしょう。少なくとも、僕は彼女に恨まれる理由なぞ持っていなかったし、こんなところにいて今まで見つからなかったのはおかしいでしょう。 僕は商売柄と言うわけじゃありませんけど元々、好奇心が強い方なんですよ。それで、僕は思い切ってその女に声をかけてみました。そうです。ええ、声をかけたんです。 『何か用ですか?』 女は、声をかけられたことに驚いたようでした。どうやら、彼女が睨んでいたのは不特定多数の人間だったらしいですね。彼女は声をかけてもらったのがよほど嬉しかったんでしょう。その顔に凄絶な笑みをうかべましたよ。ぜひとも、あの笑みはお見せしたかったですね。なぜですかって?あれほど、芸術品のような笑みは、そうそう見れるものじゃありませんよ。 『何処へいくの?』 女は聞き取りにくい、低い声でした。はっきり言って、僕のセリフの答えにはなっていませんでした。僕が答えずにいると女はしつこくまた尋ねました。 『何処へいくの?』 そう、言われても、僕は何の目的意識もありませんでしたからね。ただ、趣味のいい店でもあったら入ろうかなと考えていた程度だったんで、それを正直に話すことにしました。これくらいなら、知られたって、どうってこと無いでしょう。 『別に、何処へ行くって決めてるわけじゃありませんが。それが、何か?』 僕は店の軒先に入って、持っていた傘をたたみました。そうした方が話をするのに楽でしたからね。そういえば、あの女は店の軒先に入れば雨が避けられたのに、そうはしていませんでしたね。 『じゃあ、連れて行って』 『何処へ?』 『ここへ』 女は自分の背後の店を指さし、紅い唇を三日月型に歪ませて、にたぁと僕に笑いかけました。不気味な笑いでしたよ。地獄の笑みってやつですかね、あれは。 『私では、入れないの。だから、連れて行って』 『なぜ、入れないんです?わけを話してくれませんか』 『怖い奴がいて、私たちでは入れないの』 彼女はそう言って、身を震わせた。 『怖い奴?』 『そう怖い奴がその扉の中にいるの』 その時でした。僕は気づいたのです。そう言った彼女の首に紅い線が走っていたことに。そして、何かが滴ってきていたことに。赤い液体。血でした。血は彼女の目、口からそして首のあたりからまるで絵に書いたように美しい線を描いて滴っていたのです。 そして彼女たちは霧雨の中に溶けるように、消えたのです。でも、僕の周りに彼女達がいるのは解っていました。どうやら、僕がその店に入るまで付きまとうつもりなのでしょう。霧雨の音の合間に彼女達の声が聞こえました。 『連れて行って』 『連れて行って』 『連れて行って』 彼女たちは、合唱するのです。『連れて行って』と。 信じられない話ですか?まぁ、普通はそうでしょう。僕が夢か幻覚を見ていたんじゃないかって。本当に、そうでしょうか。彼女は僕が作り上げた空想の産物だと、そう言うんですね。 その後、僕がどうしたと思います?仕方なく僕は、その店のなかに入ったんですよ。その店は隠れ家のように、ひっそりとした店でした。初老のマスターがひとりで経営している店でね、調度品や雰囲気もなかなか良い店でした。 その店は、『薔薇の葬列』と言う混合酒が美味しいと評判の店でした。この店と同じですね。同じように初老のマスターに隠れ家のように、雰囲気の良い店。どうしました?顔が青いですよ。 それで、女はどうしたですって? ここにいるじゃありませんか。ほら、僕の周りに彼女達はいますよ。解りませんか。そういえば、あなたはこの『薔薇の葬列』を作るときに隠し味にそこの樽から何かを入れましたね。いったい、その中には何か入っているんです?言えない。言いたくありませんか。仕方かおりませんね、じゃあ僕が言いましょう。 男はそう言うと、身軽にカウンターを飛び越えると樽に貼られていた魔除けの御札を剥がした。この御札があるために、彼女たちはここには入れなかったのだろう。男はにこやかに笑いながら、手のなかにある紙を細かく引き裂いた。次の瞬間、件の樽の中から華奢な女のものと思われる白い手が何十本も現れる。濡れた白い手。白い手は蛇のように延びる、延びた。そして白い手は、マスターの躯に絡みつくように巻きつく。彼には悲鳴すら、あげる暇さえ与えられなかった。躯に巻きついた何十本の白い手は、マスターの躯を樽の中に引きずり込んだ。有無を言わせず引きずり込む。樽の中の液体は、マスターが抵抗しているかのように波うって揺れていたが、暫くするとそれも消えた。消える。 静まり返った樽の中、店の中。男はその様子を微笑みを浮かべて眺めていた。見る者の背筋を寒くさせる笑み。 「それでは、失礼します」 男は樽の中に向かって別れの言葉を言う。カウンターの上に、『薔薇の葬列』の代金を置く。樽の中からは何も返事はない。樽の中身はマスターを手に入れて、すっかり憑きものが落ちたかのようである。男が手のなかの御札を破いた。微かに聞こえる女たちの咲笑。女たちの咲笑が空中に漂っている。男は低い声で笑うと、腫を返して外へ出ていった。 (カラン、カランカラン) その日を持って、お店は無期閉店。 この後、彼が依頼人に行方不明になった婚約者のことをどのように説明したのかは解らない。 どうですか?店主は女を殺して、その血を隠し味にしていたんですよ。おやおや、お嬢さん。すっかり、青くなっているじゃありませんか。怖かったですか?それとも、怯えているんですか。うちの売り物も同じ『薔薇の葬列』と言う名前の混合酒ですからね。怖がってなんかいないって?嘘をついてはいけませんよ。私には手に取るように解るんですから。フフフ、大丈夫ですよ、お嬢さん。そんなことは、しませんよ。バレてあんな羽目になるのは二度とごめんです。あんなところに十年もいるものじゃありませんよ。もう少しで、悪夢の中で気が狂うところでしたね。今度はもう少し、上手くやりますよ。お嬢さんなら、とても良い隠し味になりそうだ。 そうそう、この度、ようやく店を再開することになりましてね。あの女だちから逃げだすのに、かなり苦労しましたよ。しつこくてね。これでも、私には少々ばかり心得がありましてね。あの男が手伝わなかったらであんなことにはならなかったのにと思うと、夜も寝れませんよ。ああ、女たちも、あんな男に引っ掛からないでおとなしくしていれば、良かったのに。 私としては、その可愛い顔がおびえる様が見たいんですよ。恐怖に歪む顔を見ると、私の躯が疼いて、快感を覚える。それが止められなくてね。しかも、彼女達の血を入れた『薔薇の葬列』はとても美味しくなると評判になりましたので、何人もの女を血祭りにあげてきました。趣味と実益が同時に上げれるんですからね、止めれるわけがないでしょう。 ねぇ、お嬢さん。せいぜい、その可愛い顔を怯えさせて、怖がって、私を悦ばして下さいよ。ねぇ、お願いだから…。 その時だった。 扉の開く音と、来客を知らせるベルの音。新しい客の登場。表の涼しい空気が強引に店内に押し入ってくる。どうやら、いつのまにか外では雨が降りだしたらしい。霧雨のようなものが扉の中に吹き込んできた。 「お待たせしました」 若い男の声。マスターは聞き覚えのある声に、入口の方を振り返って見た。そこには見覚えのある若い男が立っていた。少女はにっこりと破顔すると駆け寄る。男はマスターににっこり笑いかけた。 「お久しぶりですね」 そして、マスターの恐怖の日々が再び始まった。 |


|
|
|
|
Copyright (C) 2006. Mangougasa. All Rights Reserved. |