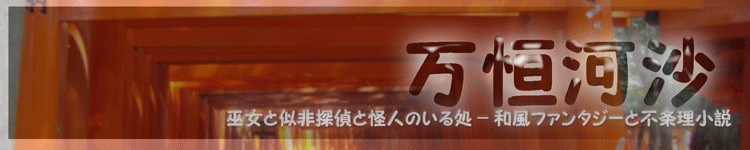
|
| ご案内 | オフライン | さかきちか創作部屋 | ツカノアラシ創作部屋 | LINK | 管理人日記 |
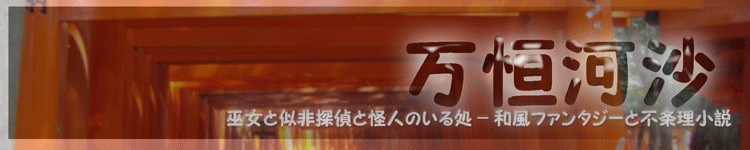
|
| ご案内 | オフライン | さかきちか創作部屋 | ツカノアラシ創作部屋 | LINK | 管理人日記 |
|
黒薔薇男爵の逆襲日曜日のうららかな昼下がり。毎度お馴染み清廉潔白探偵事務所の奥にある玲個人の書斎。怪奇猟奇事件専門の事務所はいつもの通り閑古鳥が嗚いていた。ただし、閑古鳥が鳴いていたとしても余り困った様子でないので良しとする。そして、これまたいつもの通り黒い和服の玲は怪しげな題名の本の読書にいそしみ、灰のパンツスーツに黒いシャツ、そして白いネクタイと言うマニッシュな恰好の探偵事務所の調査員の鬼堂篁はソファーの上ですっかりだれきって、執事の巽が三時のお茶の用意をしている場面からお話は始まる。ばたん、ばたん。書斎の扉がこれでもかと勢い良く開かれる騒々しい音。そして、ぱたぱたと階段を降りる足音が続き、のどかな光景を台無しにする。どうやら、何か大変な事が発生したらしい。 「ご、御前っ。た、大変ですっっ。予告状が参りました」 黒いワンピースに白いエプロン、そして白いヘッドドレスの古風で典型的な女中姿の鮎川紗雨が慌てふためいて書斎の螺旋階段を降りてくる。彼女の手には、黒い薔薇の紋章が刷られた白い封筒が一通。肩で息をしながら紗雨が玲に手渡した封筒には、ご丁寧なことに表書きに『予告状』と書かれている。どうやら、ずいぷんと単刀直入な物言いの人物が差出人らしい。この突然の始まりに室内の登場人物たちに厭な予感を抱かせたのだった。そう、良く考えてほしい。どこの世の中に、何も前触れの事件がおこっていないのにも関わらず、探偵に予告状を送りつけてくる犯罪者がいるだろうか。通常ならば、予告伏を送りつけられた流行の衣装で装った美しい被害者(女性であることが望ましい)が怯えながら探偵事務所に訪れるトコロなのである。そして、探偵に送られてくる手紙は怪人からの『挑戦状』と相場が決まっているのだ。そうあるべきである。「どこの誰ですか。そんな手紙を送ってきたのは」 玲は性別不明の綺麓な顔を微かに歪ませた。いや本当は何処の誰が送ってきたのかは想像がついていたが、自分からは言いたくなかった。大概の事は面白がる人物にしては珍しい事もあるものである。よほど相性が合わない相手なのだろうか。 「黒薔薇男爵です」 玲の質問に対する紗雨の答えは簡潔なものだった。それもそのはず、手紙の裏書きにはちゃんと差出人の黒薔薇男爵の名前が明記されていたからである。さて、黒薔薇男爵とはいったい何者か?説明しよう。彼は、気障でナルシストで、その上男色家の犯罪者という絵に描いて花マルを貰ったような怪人物なのである。え、何故男色家も絵に描いたような犯罪者に含まれるのか?それは、相場です。相場。怪人と男色家は、かの二十面相がそうであったように切っても切れない仲なのであります。おそらく、たぶん。 「……何を言っているんだか。それで、予告状には何か書いてあるんです」 うんざりした様子を玲は陽そうともしなかった。扇で顔の上半分を隠してため息をついている。他の面々もまた同じようにため息をつく。それも無理はない。いきすぎた怪人なんてシロモノは、はっきり言って人騒がせで迷惑な存在なのである。 どうせならば、セオリー通りの怪人が現れても罰は当たらないとも考えられるが、この話は不条理で出来ているのでそんなことはないのでございます。そんなことは、どこかに置いておいて。玲に言われて、紗雨は予告状の文面を読みはじめたのでありました。 「本日、午後三時に貴殿に逆襲したく参上する所存。つきましては、三時のおやつを用意して待っていて下さるようお願い致します」 紗雨は手紙を読みおわると不思議そうな顔をして可愛らしく首を傾げた。周囲に覆いかぶさる微妙な沈黙。玲はあらぬ方向を見ながら溜息をつき、篁は悪いものでも食べたかのような微妙な表情をしていた。何かが、おかしい。突っ込み所満載の内容の予告状である。だいたい逆襲しに来ようとしている筈なのに、もてなしを要求する予告状なぞ、そうそうお目に掛かれない。 「……まさか、三時のおやつを誘拐するつもりではないでしょうね」 巽が心配げに言う。因みに本日のお三時は、洋梨のタルトであった。玲の執事である巽のお菓子作りの腕はそれは見事なものなのである。その件のタルトも見た目と言い、匂いと言い天下一品ものであった。しかし、どんなに美味しいお菓子であっても、さすがに誘拐まではしないと思うが如何。 「あのな、巽ちゃん。なんで、黒薔薇男爵が三時のおやつを誘拐せにゃならんのだ」 篁の呆れたような声。篁はソファの上から起き上がると猫のように大きくのびをした。やはり、清廉潔白探偵事務所にて、まともな人物の部類に入る篁の意見は冷静そのものである。まぁ、普通は篁のように考えるのが当然だろう。 そこへ、警視庁猟奇課警部神田川一生が地味に登場。またしても、いつもの通り三時のおやつ目当ての登場であった。それにしても、一応警部さんとあろうものが、こう頻繁に民間人の家に現れて良いものなのであろうか。よほど神田川の所属する猟奇課はヒマなのだろう。 「うるさいな。これがご都合主義ってものだよ。そういえば、黒薔薇男爵から予告状が来たんだって」 「……なんでそのことをご存じなんてすか、警部さん。さては、警部さん。実はあなたが黒薔薇男爵だったんですね」 玲は手に持っている紅い曼珠沙華が描かれた黒地の扇で、神田川を指し示す。やはり、探偵ものにはこういうシーンがつきものだろう。一回くらいはあっても良い。ただ、困ったことに、今の状況はかなり変なのは確かである。 「ま、待てっ。だから、ご都合主義だって言っただろ。ほれ、俺はこれを読んでたから解ったんだってば」 神田川は慌てて持っていた冊子を珍に差し出した。珍はその冊子を受け取ると、手早くページを捲る。そして、その顔に理解の表情が浮かんできた。 「なるほど。『黒薔薇男爵の逆襲』の原稿ですか。くだらない。いったい作者は何を考えているんだか」 玲はそう言うなり、その冊子を燃やした。冊子は、あっという間に灰に成り果てる。因みに神田川はいったい冊子を燃やした炎がどこから現れたのかついぞ解らなかった。全ては、東洋の神秘がなせる技だった。しかしながら、冊子を燃やした所位では話はどんどん進んでいくのである。 「何のことだ?君らしくもない」 神田川は小首を傾げて不思議そうに肩を諌めさせた。しかし、単純構造をしている神田川のことである、すぐに思い直したようにこう言った。 「そんなことよりも、黒薔薇男爵のやつめ、三時のおやつを誘拐しようとするなんてなんて凶悪なんだ」 神田川は握り拳をこれでもかと強く握りしめ、あらぬ方向に視線を向けたのであった。どうやら、科白の内容は本気らしい。確かに、神田川はひとも驚く甘党ではあるが、さすがにその科白は何か遠うだろう。清廉潔白探偵事務所の人間から見れば神田川は常識人ではあるが、傍から見れば彼も十分ヘンである。 「おいおい」 篁が右手で顔を半分隠し、左手を上下に振る。唇に浮かぶは苦笑。どうやら、今回この中でマトモな思考をしているのは、篁と紗雨だけらしい。本当に、困ったものである。 「どうかしましたか、紗雨お姉さま」 玲は、紗雨の様子がおかしいことに気づき、優しげな口調で声をかける。玲は一部の人間を除いて自分よりも年上の相手に対しては『お姉さま』、『お兄さま』と呼びかける。どうやら、巽からそう躾られたらしい。因みに実の姉や兄に対しては『姉さん』、『兄さん』と呼びかけるので、玲の中では一応色々と区別があるらしい。 玲の呼びかけで、皆の視線が紗雨に集まる。紗雨は、どきまぎしたように頬を染めて顔を赤くした。そして、彼女は物凄く申し訳なげに□を開いた。 「あのー、少しよろしいですか?あたし思うんですけど。先程から流れている音楽は、なんなのでしょうか」 紗雨は唇の右横に人差し指を当てて不思議そうに小首を傾げた。なかなか可愛い仕種である。清廉潔白探偵事務所の心のオアシスとうたわれるだけのことはある。それにしても、なぜゆえ清廉潔白探偵事務所の所員は女性の比率の方が高いのだろうか。そんなことはどうでも良いが、確かに紗雨の言う通り、どこからともなく音楽が流れてきている。その上、だんだんその音が近づいてきているのだった。 「エルガーの『威風堂々』ではありませんか」 のほほんとした春の陽だまりのような巽の声。まるで優雅に世間話でもしているような調子だった。どうやら、この人だけ何処かの別世界にいるらしい。 「巽、紗雨お姉様はそんなことが聞きたかったんじゃないとおもうけど」 玲が執事に横目で軽く睨みながら苦笑いを向けた、その時だった。突然、窓から小型の戦車が飛び込んできた。目を疑い、呆然唖然とする光景。慌てて戦車を避ける五人。戦車は窓際の玲の机を破壊しながら書斎の中央まで進んでくるとそこで止まったのである。なかなか見事な運転の技術であった。 戦車の天蓋が開くと、無口な黒薔薇男爵の執事の老神埼が降りてきて床に赤い絨毯を敷いたのであった。その皺が刻まれた顔は、澄ましたような無表情。続いて、どこかの吸血鬼紳士のような夜会服に身を包んだ痩せ型で長身の男が優雅な動作で現れる。この人物こそ、話題の『三時のおやつを誘拐』に来た黒薔薇男爵その人だった。黒薔薇男爵は偉く気取りまくった物腰で、絨毯の上に降り立った。劇ががった態度でマントをはためかせながらくるりとお辞儀をした。 「御機嫌よう、諸君。驚いたかね」 黒薔薇男爵の声が部屋中に響く。窓どころか壁ごと開けられた穴から入ってくる風に黒薔薇男爵の黒い光沢のあるマントがはためく。マントの裏地の赤が目に染みるほどであった。『威風堂々』は止められ、今度はラヴァルの『ツィガーヌ』の演奏が始まった。いつの間にか穴からは正装した演奏家達がずらっと並んでいた。どうやら、演出効果のために黒薔薇男爵に連れて来られたらしい。良くぞこの書斎の中に全員入れたものである。 「ここは五階ですよ。どうやって飛びこめたんですか」 玲の珍しく常識的な質問。口元を扇で隠して、目だけで笑っている。なにはともあれ、結構楽しんでいるらしい。篁が一応、元窓の残骸から外を覗くが、どう考えても戦車が突然豪快に窓から飛び込めるような仕掛けはなかった。この質問に対して、黒薔薇男爵は厳かに頷いて答えた。 「私の辞書には不可能と言う文字はないのだ」 黒薔薇男爵は黒い辞書をどこからどもなく取り出してページを開いて差し出し、胸の所に左手を当てたポーズを作る。ちなみに、辞書の『不可能』の欄が黒く塗りつぶされていた。いいんだ、それで。ここはせめて自分仕様の辞書を作って欲しいものである。それにしても、あくまで非常に気取ってはいるがどことなくおかしいような気がしないでもない。どうやら黒薔薇男爵は冗談ではなく、本気で言っているらしい。彼の目は真剣そのものであった。真剣すぎて怖いくらいである。 「……どこぞのナポレオンかい、おまいは」 と、呆れたような口調の篁。因みに状況について行けない神田川はすでに目を点にして、いますぐにでも石化状態に突入しそうだった。本当に、学習能力のない輩である。これでいいのか、神田川。もう少し慣れても良い筈である。 「お姉さま、何を仰っているんですか。さすがに、ナポレオンでも戦車で五階の窓から突っ込めないと思いますけど」 玲が澄ました顔で冷静に言う。目を猫のように半眼にし、黒薔薇男爵を呆れたように眺めている。さすがの玲も黒薔薇男爵の行動に呆れたらしい。しかし、何か感じ方が違うような気がするのは気のせいだろうか。 「東洋の神秘と謎に決まっておろうが。そんな細かいことを気にしているとロクな大人にはなれんぞ」 黒薔薇男爵は偉そうな態度を崩さすに、よく解らない事を言って誤魔化した。煙に巻いたと言いたいところだが、ただ単に誤魔化したつもりになっていた。見事な自己完結である。 「……黒薔薇男爵の言うマトモな大人っていったいどんなヤツだろうな」 玲は隣に控えている巽に黒薔薇男爵に聞こえないように小声で尋ねる。少なくとも黒薔薇男爵が普通のマトモな大人とは思えない。思えるものではない。いったい彼の基準はどうなっているのだろうか。一度、詳しく聞いてみたいものである。巽は軽く肩を煉めると、やはり小声で返事をした。 「少なくとも、一般的に言うマトモな方ではないと存じますけど」 ついでに言わせて貰えば、巽も一般的に言うマトモな大人ではない。だいたい、この話に一人でも一般的にマトモな大人が出ているだろうか。いや、一人も出ていない。恐らく、たぶん。 「おいおい。何、そこで悠長に会話しているんだよ」 篁の呆れたような科白に、一瞬だけ巽は篁の方を見た。にこやかなのに、微妙によそよそしい視線。その視線を受けて篁はしまったと言いたげな顔になった。軽く舌を出してあらぬ方向を見る。逃げれるものなら、いますぐ逃げたいようなそぶりを見せる。しかし巽は篁の様子をあからさまに無視して玲の方に向き直ると、こう言ったのである。 「そうですね。お茶が目茶苦茶になってしまったので、滝れ直して参ります。何かよろしいてございましょうか、玲様」 「茉莉花茶が良いかな」 「畏まりました」 玲は少し考えてから巽を見上げながら答える、それに対して巽はにっこりと優しく笑って慇懃なお辞儀をした。それはそれは、現在の状況を抜きにすれは長閑で平和で心温まるような会話そのものだった。一体全体、何を考えているんだろうか、この主従は。 「……だからさ、そんな悠長な場合じゃないって言ってるんだけどな~」 間抜けな主従の会話に、篁は再び苦笑する。苦笑するしか術はなかった。巽は軽く篁を一瞥すると、何も言わずに玲の注文の茉莉花茶を用意するために、書斎から退場してしまう。一方、執事に一瞥された篁と言うと、苦笑を浮かべた顔を凍りつかせた。どうやら、巽の一瞥は篁にとっては、とても怖かったらしい。一度で止めておけば良かったものの。これぞまさしく、雉も鳴かずば打たれまいと言ったところだろう。本当に口は災いのもとである。 「それで、何をしに来たんですか」 玲は黒薔薇男爵に向き直ると本来ならば黒薔薇男爵が登場をした際に、一番初めにするはずの質問をする。今更という感じもしないでもないが、ここは尋ねておくべきだろう。黒薔薇男爵は待っていましたとばかりに嬉しそうにこくこくと頷く。食いつきが良いのも程がある。ようやく話が進むと言わんばかりであった。 「決まっているではないか。三時のおやつを誘拐しにきたのだ」 黒薔薇男爵は恐ろしく厳かに宣言した。まるで結婚式で誓いの言葉を宣誓しているかのようだった。どいつもこいつも。しかし、本当に冗談でもなく『三時をおやつ』を抜け抜けと誘拐しに来るとは、世の中侮れない。常人の理解を越えた動機だった。 「あのなー」 篁と紗雨が、その場で大仰にこけた。この場合、こける他に何ができようか。篁と紗雨は、何か悪いものでも食べてしまったかのような妙な表情を浮かべた。しかしながら、冗談と悪夢の産物のような玲の対応は全く違っていた。 「そのわりには、随分と派手な御登場でしたね」 玲はヒトを小馬鹿にしたような口の端を持ち上げるような笑みを浮かべる。右手に持った半開きの扇がサマになっていった。それにしても、どうしてこうして、なかなか高飛車な態度だったのは、言うまでもない。 「ついでに貴様の命も頂くつもりなのだ」 黒薔薇男爵は当たり前のように言った。それにしても、『三時のおやつ』のついでに殺されるとすれば屍人も浮かばれないような気がする。 「普通、逆じゃねーのか。命を頂くついでに、三時のおやつを誘拐だろ」 篁のつっこみ。紗雨も同感だと言わんばかりに真面目な顔をしてこくこくとしきりに頷く。いや、それでも『三時のおやつ』ではなくて、普通は金目のモノとかを強奪するのがセオリーではないだろうか。 「でもでも、それに普通は三時のおやつを誘拐ってことはないと思いますけど」 あくまで常識にこだわる篁と紗雨の二人。しかし、やっぱり二人とも何かが変である。ところで、神田川氏と言えば、見事にムンクの『叫ぶ人』と成り果てていた。 「いちいち、うるさい奴らだな。ええい、まとめて始末してやる。打ち方、打てい」 黒薔薇男爵は、手に持ったステッキを床に打ち付けて無理やり話を先に進めた。本当に傍若無人なおヒトある。黒薔薇男爵の合図で、戦車が砲撃を開始する。と、同時に玲たちは身を伏せ、砲撃から逃れた。戦車は、これでもかと言うかのような次々と砲撃をする。ただし、なぜかその命中率はナイに等しい。どうやら打ち方さんは余り射撃がお上手ではないらしい。殆どが書斎の破壊に費やされていく。何故、そんな輩に打ち方を任せているのか謎である。案外、黒薔薇男爵には人材がいないのかもしれない。 「おーほっほっほっ。いったい何の騒ぎかや、これは」 外見は十才程度にしか見えない玲の姉、夜神綺乃の登場。古風な口調の赤い着物に緑の被風を着た彼女は、まるで砲弾の嵐が存在していないかのごとくの優雅な登場である。因みに、綺乃の趣味は世界征服である。しかしながら、かつて今までその野望は一度として達成された事はない。どうやら彼女は、いつもの通り世界征服に失敗をして愚痴りにここへ来たものらしい。手には今回の世界征服計画で遣い損ねたらしい物騒な代物が入った紙袋を持っていたりする。物騒なこと極まりない。 「姉さん、いらっしゃい。残念ですけど。今は立て込んでいてお相手ができる状態じゃないんです」 玲は器用に砲撃を避けながら綺乃に声を掛ける。綺乃は状況を今初めて気がついたように、室内を見回すと感想を述べた。 「そのようじゃな。しかし、こういうシーンを見ておるとな、わらわの血が騒ぐのじゃ] と、綺乃は言うなり、紙袋から取り出した手榴弾を投げはじぬた。綺乃の高笑いが室内に広がる。何か、とても楽しそうであった。世界征服を失敗した事によるストレス発散なのだろうか。しかし、何故、何なんだこの展開は。いったい綺乃は何をしに登場したのであろうか。謎である。綺乃の道理が通らない所業に書斎に被害が増えたのは言うまでもない。どんどん目茶苦茶な展開になっていく。これで、収拾がつくのだろうか。 「どうにかならんのか、これ」 玲に無理やり手を取られて、とりあえず安全そうな場所に逃れてきた無傷の神田川が虚ろな目を戦車に向けながら言う。悪夢のような光景。神田川は少し前までの平和は状況が懐かしかった。それにしても、この砲弾と破壊の中で無傷とは神田川も意外に運が良い。 「仕方ありませんね。どうにかしましょうか」 玲は戦車の方を振り返ってにこにこしながら言った。どうやらすっかり、この鬼ごっこを楽しんでいたらしい。とんでもない輩だ。そして、玲の言葉通り、神田川の知らないウチに状況はどうにかなってしまったのである。どうやって、どうにかなってしまったのだなんて聞かないでほしい。少なくとも、黒薔薇男爵がいつもの通りにボロボロになってほうほうの体で逃げだし、清廉潔白探偵事務所が元の平和な状況にかえったことだけは確かである。兵どもが夢の跡。 そして、再び舞台は書斎に戻る。書斎の中は見るも無残な姿を晒していた。不幸中の幸いと言えば、玲のコレクションであるどこからどうやって手に入れたか解らない珍品、怪奇な本が所狭しと並んでいるものが何故か無傷だったことである。 「不幸な事件でしたね」 窓があった場所から下を見下ろしながら、玲は珍しくは物憂げな口調で言った。神田川に背中を向けているために、神田川には玲が今いったいどんな表情をしているのか解らない。しかし、玲らしくない科白であることは間違いない。思わず、神田川が自分の耳を疑ったのも無理はない話である。 「……本当にそう思っているのかな、玲くん」 玲が突然くるりと優雅な物腰で神田川の方に向き直る。思わず、神田川は身構えた。今までの神田川の経験からして、玲が何を言いだすか何を始めるか解らないからである。もはやぞ条件反射と言えよう。少し同情の念を禁じえない。玲は顔の上半分を扇で隠して、物憂げな口調で言った。 「ええ。この惨状を見た巽がどう思うか、それだけが心配で」 玲は扇を閉じて扇を右手で持ったまま両手を組んだ手の上に顎を乗せて溜息をつく。どうやら、本気で心配しているらしい。そういえば、前に玲からこの世で一番怖い事は巽を怒らす事と聞いたような気もしないでもないと神田川は思い出した。しかし、どこか問題が間違っていないだろうか。 「……本当にキミ、主人なのか」 神田川が思わず聞いたのも無理はない。実は二人の立場が逆なのではないだろうかと言うような意見だってあるくらいである。真実は如何。そこへ当の巽が目茶苦茶になってしまったお茶の替わりを持って書斎に入ってきた。少し時間が掛かったようだが、今まで彼は何をしていたのだろうか。 「もちろんですとも、神田川さん。私の主人は玲様だけでございます。ご安心下さい、玲様。黒薔薇男爵のアジトから、すでにここの修繕費用の金目のモノは手に入れてございます」 巽は澄ました顔で言った。いつもの通り優しげに見える笑みを浮かべている。玲と神田川は思わず顔を見合わせた。優しげな笑みと顔だからと言って、本当に優しいのかは謎である。巽はテーブルの上に、お茶の用意を手際良く始めた。それにしても、すでに金目のモノを強奪しているとは、随分と手際が良いことではないだろうか。いつのまにそんな事をしたのか。予期でもしていたのだろうか。思わず脱帽したくなるほどである。 「……どうやってそんなことができるんだよ」 神田川は半ば呆然としながら独り言のように言う。本当にどうしたら、そんな事ができるのだろうか。どのような手段を取ったのか考えるだに、恐ろしい事この上なしである。ありとあらゆる汚い手段を取ったに違いない。まあ、悪党相手なので、深くは考えずに良しとする。 「警部さん、そんな事を僕が知っているわけないでしょう」 神田川の独り言のような質問に、玲は肩を竦める。巽はもちろん神田川の質問には答える気は全くないらしい。平然としたものだった。さすがボケてるいるのに、性悪な男と言われるだけはある。神田川に諦めの表情が浮かぶ。世の中、知らない方が良いことは山ほどあるのである。 「すでに受領書も先様には送っておりますので、今頃は黒薔薇男爵はここを破壊したことを後悔しているところでございましょう。それでは、お二人ともお茶にいたしましょうか」 巽はそう言ってにっこり笑うと、新しく用意されたテーブルにお茶の用意をし始めたのであった。清廉潔白探偵事務所で一番怖くて影の実力者なのは、多分この男であろう。いや、もしかしたら登場人物中でもかもしれない。触らぬ神に崇りなしとは、よく言ったものである。 黒薔薇男爵の災難古風な五階建てのピル。ガーゴイルのような石造が柱に飾られている石段を上り、レリーフの付いたガラス戸を開けると、荒れ放題ホールが広がる。どうやら、見た目は廃ビルのようである。しかし、顔の見えない誰かは、迷わず昇降機と呼びたくなるような、エレベーターヘ入る。キイキイキイ。軋む音、音。停止階は五階。昇降機の罪が開くと、そこは驚くべき光景だった。黒と白の市松模様を描く大理石の床。一階とは正反対な滝洒な造り。廊下の行き止まりにあるこげ茶色の木製の扉の曇りガラスには、銀色の飾り文字で「清廉潔白探偵事務所」と書かれていた。銀のドアノブに掛けられた『怪奇・猟奇事件あります』と書かれた黒い札が風もないのに揺れていた。 うららかな昼下がり、清廉潔白探偵事務所ではうららかなな気候とは裏腹に、最悪な二日酔いに苦しんでいるヒト達が二人程いたりする。清廉潔白探偵事務所調査員の鬼堂篁と警視庁猟奇譚警部さんである神田川一生は、小悪魔と称される所長と性悪な執事が留守であることを良いことに、鬼のいぬ間の洗濯と称して、昨夜から終わりの見えない宴会を繰り広げていたのである、これを自業自得と俗に言う。酒の空堰の数々の中に、ケーキ箱やお菓子の残骸が散らばっているのは、甘いものに目がない誰かさんのご愛嬌か。 黒いワンピースにレースのエプロン、そしてヘッドドレス姿の古式ゆかしい女中さんの登場。 女中さんは、まったりとしている二人を見下ろして大仰にだめ息をついた。目の前には駄目駄目大人が二人。女中さんこと鮎川紗雨はすっかりだれている「こんな大人になるものか」と二人に構わず、容赦なくカーテンを全開した。吸血鬼ではないが、日の光りが眩しい。篁と神田川が抗議の声を上げるが、紗雨は全く取り合わない。そして、澄ました顔で、依頼人が現れたことを告げた。それも、どうやら紗雨の口ぶりでは奇妙な依頼人らしい。 「仕事なら、御前に。ちっ、そうか御前は仕事か」 不機嫌そうな篁の声。篁は、ため息をついて寝ころんでいたソファから立ち上がると、こめかみに指を当てながらソファの上に放置されていた灰色の上着を取り上げ、緩んだネクタイを締め直す為に手をかけた。乱暴な言葉使いと、男のような恰好の篁は嫌々ながらも、漸く事務所の方に顔を出す気になったらしい。しかし、篁は事務所には行かずに済んだ。なぜなら、松風と村雨が止めるのも聞かずに依頼人が待ちきれずに勝手にこの書斎まで来てしまったからである。それにしても、困った依頼人である。 さて、茉莉花茶をどうぞ。 「ワタクシ、白井百合子と申します」 茉莉花茶が滝れられた茶碗を前に、依頼人である白い貴婦人は鈴を転がすような声で自己紹介をした。乙女チックな白いレースの日傘を室内で差し、縦ロールの髪を覆うレースがふんだんに使われた白いボンネットを被り、身に着けているのはバッスルの入った白いドレス、そしてお供には白い着物を着た禿姿の美少女を二人。はっきり言って、何かがおかしい依願人である。 「それにしても、随分と乱雑なお部屋ですことね」 白井百合子と名乗った美女は書斎の中をゆっくり見回して云う。面白そうな顔だった。書斎の為に弁解するならば、いつもは決して足の踏み場が無いほど乱雑ではない。いや、それどころか書斎の主が乱雑にしている最中でなければ几帳面な執事のおかげで恐ろしいほど綺麗なのである。 「アンタが勝手にこの部屋に入って来たんだと思うが」 篁が性悪執事に対して多少後ろめたさを覚えながら、厭味を言うが百合子には効き目がないらしい。涼しい顔の百合子を見て「また何でこんな厄介そうな客が来たんだ」と篁はため息をつきながら、茉莉花茶が入っている茶碗に口をつけた。どうやら、気を落ちつかさせる為の動作らしい。そして、今ここに御前がいれば嬉々ととしてトチ狂った依願人の相手をするだろうにと、御前が運悪く留守なのを少しだけ恨めしく思う。なんとなく、八つ当たりの上に逆恨みのような感もしなくはない。 「それで、ご依頼の件とは」 篁は七転ハ倒の後に、漸くため息をつきながら自分にふりかかった運命をおとなしく甘受することにした。諦めが大事とは良く言ったものである。 「ええ、実はここに来たのは、黒薔薇男爵と名乗る厭な男に会えると聞いたからですわ」 百合子は少し頬を染めて恥ずかしげに口許を縁に羽付きのピンクの扇で隠した。それにしても、妙な雲行きになってきた。因みに黒薔薇男爵とは気障でナルシスト、その上男色家である絵に描いたような世紀の犯罪者なのである。その黒薔薇男爵と依頼の関係は?その上、どうやら彼女の様子から見て黒薔薇男爵に脅迫されたとか、予告状が来たとかいうものではないらしい。そもそも黒薔薇男爵は女性を獲物としない。篁がなんとなくトラブルの予感を感じたのは言うまでもない。 「ワタクシ、とっても黒薔薇男爵を恨んでますの。恨み過ぎて、手錠に猿ぐつわをしすまきにして、神田川に叩きこんだり、車に爆弾をしかけたりとお茶目な悪戯をしてしまいますのよ。お恥ずかしいわ」 百合子は、レースのハンカチを握りしめながら更に頬を桃色に染め恥ずかしそうに躯をくねらせた。今の話が事実だとすると、彼女は黒薔薇男爵と負けない位の人物だと言うことだろうか。篁は厭な気がした。そして、それを聞いた神田川と妙雨は、百合子と禿に背中を向けると小声で会話を交わす。 「お茶目な悪戯か、ソレ」 と、神田川。すでに彼は目が点になっている。いつになっても、この清廉潔白探偵事務所での奇妙な出来事に慣れない神田川であった。しかしながら、そこが神田川の良い所なのかもしれない。 「一歩間違えば、普通は死にますよね」 と、紗雨。しかし、相手はあの黒薔薇男爵である。侮るなかれ。篁は二人の会話に軽く眉を輩めると冗談めかしたロ調で、白井百合子に先程から脳裏に浮かんでいたあって欲しくないことを質問した。 「それで、もしかして貴方。実は宿敵の白百合女侯爵とか名乗るんじゃないだろうね」 「何故、お解りになりましたの」 白井百合子と名乗った女はごく真面目な顔で、不思議そうに小首をかしげた。一瞬、怖いくらいに書斎の中が静まる。篁はうんざりした顔をし、紗雨は笑顔のままその場で固まり、そして神田川は目を点にしてあらぬ方向を見ていた。 「お言葉なんだが、ウチは黒薔薇男爵の連絡先じゃない」 篁は投げやりになって言った。その時、女中さんその一の松風が部屋に入ってきた。捧げ持った銀のプレートの上には手紙が一通。篁は気の進まないような顔をして、松風から手渡された手紙を開く。中から、黒地に銀の薔薇の縁取りしたカードが出てきた。カードには、端的に用件が書かれていた文。 「何々、黒薔薇男爵参上。よりにもよって、皆して御前のいない所に来るんだ。何かの罰ゲームか。こんな状況、御前なら喜ぶだろうけどアタシは遠慮したいぞ、はっきり言って」 篁は黒薔薇男爵のカードを思いっきり力任せにびりびりに破いた。カードは千切れて床に落ちる。八つ当たりでカードを破くことくらいしか、今の篁にはできなかろう。鬼の居ぬ間に命の洗濯のつもりがとんだ結果になりそうである。 「あなた方、ワタクシの事無視していません?」 白百合女侯爵は憤然と周囲に向かって抗議をした。口元がぴくぴくと小刻みに震えている。どうやら、彼女は自分が話の中心でないと許せないお人らしい。困ったものである。 「いやー、見たくない現実って逃避するでしょ」 篁が更に投げやりに言ったその時だった。いかにもと云うパイプオルガンの音か何処からともなく聞こえてきた。それも、床下の方から聞こえてきているようである。篁が厭な予感に駆られ、神田川と紗雨が顔を見合わせたちょうどその時、登場時期を狙ったかのようにばたんと書斎の床が開いて、黒薔薇男爵はパイプオルガンごとせり上がってきた。どうやら、性悪執事がいないことを良いことに黒薔薇男爵は勝手にせり上げを追ってしまったらしい。見事なものである。恐らく、せり上がりの下では黒薔薇男爵の部下がぐるぐると何かを回しているに違いない。 「いつのまに、ヒトの家をそういう風に改造したんだ」 篁は頭痛を覚えながらも、黒薔薇男爵を怒鳴りつけた。 「怖い性悪執事が留守の内に造らせてもらった」 黒薔薇男爵は、真面目な顔で答える。痩身で長身の上に端正な顔をした黒薔薇男爵は、オールバックにまるで吸血鬼が着ていそうな黒いマントと燕尾服姿と言う絵に描いたような悪役姿であった。ただし、言動は他人の家にせりあがりを追ってしまうことから考えてもこの人ももれなくかなりおかしい。 「やはり現れましたわね、黒薔薇男爵。ごきげんよう」 黒薔薇男爵の目の前に立ちはだかる白い影。もちろん、白百合女侯爵である。他の三人はやる気のなさそうに見物する事にしたらしい。白百合女侯爵はにっこりと微笑んでドレスの裾をふんわりと持ち上げて宮廷風のお辞儀をする。どうやら、いくら宿敵と言えども挨拶はしておくべきだと考えているらしい。 「そこにいるのは、白百合女侯爵ではないか。久しいな」 黒薔薇男爵と白百合女侯爵は優雅に挨拶しあった。それはそれは、状況にそぐわない姿である。 「今日こそ、決着を付けに参りましたのよ」 白井百合子こと白百合女侯爵は、バッスル入りのドレスをここぞとばかりに脱ぎ捨てた。禿達が慌てて、脱ぎ捨てられたドレスを回収する。どうやら可愛らしい禿さん達はこのタイミングのためにいたらしい。ドレスを脱ぎ捨てた白百合女侯爵は19世紀の下着姿になった。腰には百合のレリーフがされたレイピアを下げている。なかなか魅惑的な姿である。白い下着が目にも眩しい。様式美と言うものだろうか。 「そのような姿を見せても、私には無駄だぞ」 黒薔薇男爵は冷ややか目で白百合女公爵を見ると吐き捨てるように言った。確かに、無駄だろうな。理由は云わずもがな。 「汚らしい殿方の為に、このような姿になったのではありませんことよ。これはワタクシの戦闘服ですわ」 白百合女公爵は軽蔑のまなざしを黒薔薇男爵に向けた。個人的な感想を言わせてもらえば、彼女の姿は戦闘服と言うよりも怪我の元である。良い子は、真似してはいけませんよ。すっかり二人はよそのお宅で私的な闘いを始めんとしていた。非常に迷惑な事、この上ない。 「もしかしてさ、これ趣味趣向が相容れない人たちの争いか」 はたと思い至った篁はぽんと手を叩くと疑問が氷解したような顔をした。なるほど、二人は相容れないワケである。しかし、はっきり云ってそんなこと理解しても余り嬉しくはない。そこへ冷たいまなざしが篁に突き刺さる。 「お姉様。もしかしなくても、その通りでしょう」 「よく解らない世界だ」 神田川が頭を抱える。うつろな目つきが、彼の現在の精神状態を如実に表していた。しかし、展開は神田川に容赦なかった。史上最大のはた迷惑な闘いは、黒薔薇男爵の執事の老神崎がいそいそと用意した蓄音機が奏でるドボルザークの『新世界』を合図にして始まったのである。 「くらいませ、白百合乱舞」 レイピアを抜いた白百合女侯爵が、レイピアを上に捧げて左右に振る。すると何故かどこからともなく現れた白百合の嵐がそこらじゅうを席巻しだした。乱れ飛ぶ白百合。それは見事な光景だった。 「なんの、黒薔薇魔方陣」 これまた、いったいどのような仕組みになっているのか解らないが、黒薔薇男爵が呪文らしきものを唱えると黒薔薇男爵の足元の床に青白い光りで魔方陣らしき物が描かれたと思うと、黒薔薇が部屋中に乱れ飛んだ。こちらも、同じく豪華スペクタルな光景である。 しかし、やはり迷惑なことこの上ない。 書斎の中は白百合と黒薔薇の嵐。元々、乱雑だった書斎が、輪を掛けて乱雑に成り果てていた。性悪執事がこの光景を見たらと思うと考えるだに恐ろしい。 「人知を越えた闘いだな、ありゃ」 篁が黒薔薇男爵と白百合女侯爵の死闘を見ながら、妙に感心したように言った。確かに、ここまでなると感心するしかないかもしれない。手も足も出ないとはこういう状況を言うのだろう。 「外見は、ダンディなおじ様なのにあんなに奇人変人で残念ですよね」 諦めたような顔の篁と紗雨。二人は、いち早くソファの下に避難してこの光景を高みの見物と決め込んでいた。因みに、神田川くんはは先程かた壁に向かって正座をして何やらぶつぶつ呟いていた。彼はすっかり壊れてしまったらしい。 「あっちだって、外見は貴婦人だぜ」 篁はレイピアを振り回している白百合女侯爵を指さす。白百合女侯爵の周りでは何故か、禿の少女達が扇を持って踊っていた。よく解らない世界である。篁と紗雨は顔を合わせて、何となくため息をつく。 「お姉様方、そもそもこの物語で外見と中身が一致してるヒトは少ないですよ」 その言葉に、紗雨が妙に納得したような顔をする。篁も同じく腕組みをして得心がいったように頷く。しかし、何かおかしくないかい?漸く、少々立ち直った神田川は、ふと当たり前のように会話に紛れ込んでいる人物がいることに気がつく。そして神田川は、恐る恐るその名前をロにした。 「玲君。いつから、いるんだ」 「さっきから、気がつきませんでしたか?」 容姿端麗性格破綻の黒服の探偵は楽しそうににこにこと笑ってソファに足を組んで優雅に座っていた。この光景を楽しんでいるのだろう。それにしても、この惨状をものとも思わず楽しめるとはどんな精神構造をしているのだろうか。さすが他人から性格破綻者と言われるだけはある。玲の手は茉莉花茶が入った茶碗を持っていた。 「そう言われれば、先程から会話の間に言葉使いが違うヒトが混じっていましたね」 なるほどと紗雨が手を打つ。しかし、だからと言って状況は変わりそうもなかった。その時、今度書斎の奥の罪が開いた。随分と、来客の多い日である。室内に血相を変えて飛び込んできたのは日女由貴也。巽の甥のような人物である。見た目は二人とも同じくらいの年に見えるのが本当に甥のような人物なのである。いや飛び込んできたのは由貴也だけではなかった。由貴也を追いかけるように大音響を轟かせながら現れたのは笑う大岩。どうやら由貴也はこの大岩に追いかけられて、ここに逃げ込んだらしい。それにしても、どのような手段を使ったらここに逃げ込めたのだろうか。そもそも、由貴也はどこから来たのだろうか。謎である。 そして、由貴也は身軽に窓をのりこえ、大岩は彼を追いかけ窓に突進していった。まるでサイドワンダーのようである。呪いでもかけられているのだろうか。壁が壊れる音。もちろん、大岩は引力の法則により笑いながら下に落ちていった。この後、このピルの下で何か起こったのかは考えたくもない。そして、由貴也の末路は? 「いやー危なかった。お取り込み中のとこすまないな。いや!とある神秘の森で石像を手に取ったら大岩に追いかけられてさ、目の前に何故か扉があったから逃げ込んだらこんなところに通じてるなんて、いやいや世の中侮れないねぇ」 壊れた壁をはい上がってきた由貴也は、目の前で笑う大岩現わるにも何事もなかったかのように闘いを続けている黒薔薇男爵と白百合女侯爵に動じた様子もなかった。 玲は薄笑いを浮かべて、茉莉花茶を飲む。優雅なこと殊更ない。しかし、この状況でよくそんなに優雅にしてられるものである。いったい、どのような精神構造をしているのだろうか。空になった茶碗を差し出すと、すぐさま新しい茉莉花茶が注がれた。 「それにしても、もの凄い惨状だなここ」 明るく、しかも軽く云った由貴也の台詞が紗雨と篁を現実に引き戻した。それにしても少なくとも、この惨状の一部は彼にも責任がある筈なのだが、どうだろう。たちまち紗雨は青ざめ、篁はしまったとでも言いそうな顔をしていた。できれば、影の最高実力者にお小言を言われる羽目には陥りたくはない。 「そうですね。それにどうやら、あの様子では決着はつかないんじゃありません?ね、警部さん」 玲はちろりと、闘い続ける黒薔薇男爵と白百合女侯爵を流し見る。二人とも、「黒薔薇僚乱」「白百合散華」等と新しい技を繰り出しており、まだまだこの闘いを続けるつもりらしい。困ったものである。 「なんで、君はそんなに楽しそうなんだ」 可哀相な神田川一生。普通からは逸脱しているが、ここにいる探偵を代表とする人達ほど逸脱しきれないために彼は困ったような顔をして弱ることしかできない。 「楽しくないですか?」 玲は不思議そうに小首を傾げる。妙に天真爛漫な様子。たぶん、黒薔薇男爵と白百合女侯爵の闘いも楽しいのだろうが、困りきっている神田川を見るのも同じくらい楽しいのだろう。非常に、困ったものである。その態度に、神田川は思わず頭を抱えたくなった。所詮、この探偵にマトモな事を求めても無駄な話である。 「俺はそれよりも、この状況をどうにかしないと巽ちゃんが半狂乱になるのが怖い」 「誰が半狂乱ですって?」 神田川が後ろを振り向けば、そこにはポットを持った巽が立っていた。どうやら、玲と同じくさっきからそこにいたようである。道理で先程空になった茶碗に茉莉花茶が注がれる筈である。顔には人の良さそうな笑みを浮かべているものの、よく見れば微かに片頬が小刻みに震えていた。 「た、巽ちゃん。いらっしゃったのか」 篁は慌てるあまりに言葉がおかしい。その上、壁に張りついたその姿は、いまにも逃げだそうとしているような態勢だったりする。余程、彼女は性悪執事さんが怖いのだろう。 「本当に、巽がいるのに気づいていなかったんですか」 にこにこと玲は笑った。まるで、他人事のようである。いや、本当に今回は他人事であった。 「確かに、御前が自分でお茶を滝れるなんてことはしないし。ぬかったぜ、さっさと逃げておくんだった」 由貴也が舌打ちをする。ついでに、本当にこの場から逃げようとするが、一人で責任を取るつもりは全くない篁に襟首をっかまれて逃げ損なう。不幸な事である。 「篁、貴方がいてこの状況はどういうことなんですか」 巽はそれこそ怖い位の優しげな笑顔を浮かべていた。優しげな顔で、怖いことを云いだすこと程、恐ろしいものではなかろうか。 「不可抗力だぞ、これは」 篁はそれこそ一所懸命に、言い張った。しかし、篁が巽を丸め込むことなど世の中がびっくりかえっても到底無理な相談だった。 その後、清廉潔白探偵事務所では、世にも恐ろしいことが起きたらしいが、余りの恐ろしさに詳細を語るものは少ない。聞いた話ではなんでも、あの白百合女侯爵と黒薔薇男爵が書斎の掃除をしていると云う、世にも珍しい光景が見れたそうである。 |


|
|
|
|
Copyright (C) 2006. Mangougasa. All Rights Reserved. |