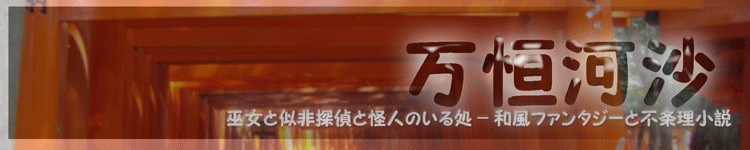
|
| ご案内 | オフライン | さかきちか創作部屋 | ツカノアラシ創作部屋 | LINK | 管理人日記 |
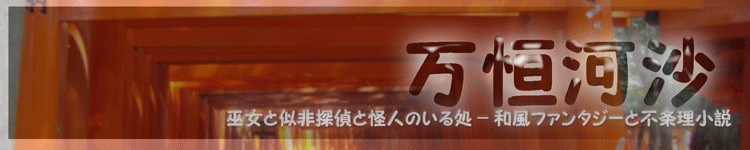
|
| ご案内 | オフライン | さかきちか創作部屋 | ツカノアラシ創作部屋 | LINK | 管理人日記 |
|
嵐の孤島鶏が先か、それとも卵が先か?それが問題だ。舞台は嵐の孤島の別荘のかなり悪趣味な応接間。隣の別室には、屍体と書かれたプラカードを手に握り締めた悪趣味なガウンを着た死体が胸の辺りを真っ赤にして倒れていた。恐らく、口には葉巻が咥えているのではなかろうか。よくある嫌味な大富豪と言う風情である。因みに、隣室の鍵は失われ、密室となっている。 彼は、どこからどうみても立派な名探偵だった。名探偵は、自分が主人公なのを過剰なほど意識していた。この日のためにわざわざ用意した、ジェレミー・ブレット演ずるシャーロックーホームズばりの衣装が役に立つ。なんでも買っておくものだと、名探偵は窓ガラスに映った自分の姿にうっとりと見ほれる。少し、ナルシストな傾向を持つお方らしい。困ったものである。外はすでに暗闇に包まれているためか、窓ガラスは姿を映すのにうってつけだった。しかし、どこからか姿見でも持ってきた方が良い気もしないでもない。 (コツ、コツ、コツ) 名探偵は少し緊張しながらもこれ以上ないほどに張り切って、舞台の中央に進み出た。演出効果のために、わざと立てられる靴音。ぐるり体を動かしながらと、舐めるように観客の顔を見回す。館に居合わせた七人の男女の顔が緊張したものになった。名探偵を入れて、全部で八人の男女は緊張の絶頂にいた。 因みに、隣室の屍体は、この別荘の主人であった。 密室殺人。いや正確には、鍵が行方不明の部屋。屍体は何故か、核兵器が落ちても壊れない部屋の中に落ちているために触れることもできない。何のためにそんな部屋を作ったのか、しかも何そんな所でわざわざ嫌がらせのように死んでいるのか、またその死因も謎である。だからこそ、名探偵のような古典的な人物が必要なのだ。(本当か) 容疑者は七人。これこそ、自分にぴったりな事件。この日の為に、それこそ日々血がにじむ思いで練習してきたことが役に立つのだ。名探偵は容疑者の顔を見回しながら満足げに頷いた。 以下は名探偵の七人の容疑者に対しての独白と紹介のメモである。 山田良子。屍体の娘。フランケンシュタインも顔負けの白塗りのお化けのような女である。それが、自分では十分男を引きつけると思い込んでいるのだから世話がない。その上、容姿以外は男性の誤解した女性像を演じているようである。 大道寺あやめ。メイド。男好きをする妖艶な美女。まるで、ピーター・セイラーズの『マジッククリスチャン』に出てくる色っぽいフレンチメイドさんのようである。誰が見たって、屍体がお手つきしているだろうと予想される。被害者は、あんな娘を持っているわりには審美眼は良いらしい。 宮城高次。執事。漂白したような白い手袋が似合った、いかにも絵に書いたような執事姿。顔の全ての部分がVで出来たような顔をしている。年は三十才を越したくらいか。執事としては、少し若いのが気にかかる。 藤井則夫。弁護士。でっぷりと太った冴えない中年男。いつでも、何か口に入っていないと気が済まないらしいと見え、どこから用意したのか今もひとりでフルコースを食べている。もしかして、自分で製造、消費しているのだろうか。 青柳竜衛。屍体の友人。端正な顔をした優男。顔に似合わず毒舌家で、思わず後ろから殴りたくなるようないい男である。是非とも後ほど、闇討ちリストに乗せるべきだろう。やはり、屍体の友人と言うわりには若すぎる。 青柳あきら。青柳竜衛の妹。青碧の瞳を持つかなり印象的な、ボーイッシュな美少女。ビィクトリアン風の丈の短い黒いドレスお似合い。ただし、少々もとい多大に性格に難有り。できるだけ、お近づきにはなりたくない。 神田川一生。警視庁猟奇課警部。見るからに切れ者と解る若い男。 はっきり言ってロクでもない独白である。色々な意味で自分が興味を抱いていない者にはコメントが少ない。参考にもなにもなりはしないこと請け合いであった。 「さて、皆さん。私こと名探偵が、皆さんをここにお呼びしたのは、実は…」 名探偵はもったいぶった身振りと口調で、この殺人事件の神秘の謎を解いてみせようとした。この瞬間に名探偵を襲う目眩のような快感。この快感が止めれなくて、名探偵をしているようなものである。いいのか、そんなもので。 「どうせ、犯人が解ったとでも言いたいんでしょ」 そう言ったのは、青柳あきらであった。名探偵の話の腰をあっさりと折る、冷たい口調。あきらは付け加えることができるなら、いかにも馬鹿馬鹿しいとても言いたそうであった。名探偵は相手に向かってこの悪魔と胸の中で罵ってから撫然とする。この数日の間で、この世にも珍しい性格の歪みきった美少女に名探偵は何度邪魔されたことかとはがみする。 「ヒトの台詞を取るなんて、非常識とは思いませんか、お嬢さん」 名探偵は、この場で少女を今にも殺しそうな顔つきで言った。名探偵の背後には、おどろおどろしい黒い線がのたくりまわっていたことは言うまでもない。 「だって、『名探偵、皆を集めて、さてと言い』って良く言うじゃありませんか。セオリーです」 あきらには、名探偵が取りつく島もなかった。名探偵に一歩も引かないあきらの容赦無いセリフに、周囲から失笑が洩れる。思わず名探偵は顔を恥ずかしさから真っ赤にする。しかしそこは名探偵、世界新記録並の短時間で立ち直ってしまった。なんとも残念である。名探偵はもう一度、威厳のある態度を取り戻して、何もなかったように先を進めることにした。 「犯人は、お前だ」 名探偵は娘を指さした。娘は呆れた眼差しで、名探偵を見る。そして、ゆっくりとどうやら自分では十分色っぽいと考えている動作で脚を組み換えた。彼女がどのような効果を期待したかは解らないが、はっきり言って余り嬉しくない。しかし、その余りに余裕たっぷりな態度に名探偵は辟易するものを感じた。何か、何かがおかしい。しかし、自分の推理には絶対の自信を持っている名探偵はそんな筈はないと自分に言い聞かせる。何と言っても、彼はこの物語の主人公であり、天下に名高い名探偵なのである。 その天下の名探偵が推理を間違えるはずがないし、そんなことは許されない。そして、そんなことは彼の予定にはなかった。彼の予定では、犯人はよよよと泣き崩れ、動機と謎を解いた名探偵への賛美を口にすることになっていたのだ。 「理由を言って貰おうじゃありませんか。理由を」 良子は皮肉な笑みを浮かべる。良子は自分が犯人として名指しされることは絶対にないと思い込んでいた。そう彼女には絶対、自分であるはずがないことを知っていたし、それだけの理由もあった。 「理由か、理由を言ってほしいですか?」 名探偵は、まだ優位な立場に立っているつもりだった。どことなく上調子になる神経質な声。裏付けのない尊大な自信に満ちあふれた態度。全て名探偵の自信のほどを伺わせるものだった。 「もちろんよ。アタシが犯人だって言う証明をしてもらわなきゃ、納得できないわ」 良子は思わず目を覆いたくなるようなしなを作る。いったい全体、彼女はこれによって何か効果があると思っているのだろうか。お尋ねしてみたい気もする。 「山田良子。いや、中川大介と呼ぼうか。お前は、被害者の行方不明の娘に成り済まし遺産を横取りしようと図ったのです。そして、被害者を殺し、部屋の鍵を閉めた後、その怪力で鍵を壊したのであります」 …なんて、そんな細かいことまで知っているのだろうか。それに、なぜゆえその怪力で鍵を壊さなければならなかったのだろう。そもそも、何故「息子」になりすまさないで、敢えて「娘」に成りすます必要があったのだろうか。謎である。因みに、状況としては多少の面白みがあるが、現実問題として密室殺人に意味はそれほどない。 「何故バレたの。変装は完璧だと思っていたのに」 山田良子、もとい中川大介は『がーん』と効果音が書かれたプラカードを右手比もってショックを受けていた。どうやら、自分では完璧に美しい女装姿だと自画自賛していたらしい。たぶん、彼の家には鏡がないか、もしくは彼の審美眼が恐ろしく狂っているのだろう。 それにしても、彼がショックを受けた理由は、犯人と名指しされたと言うよりも女装に関してのものと思われた。これはおかしい、おかしすぎる。 「…今まで、バレてないと思うほうがおかしいんじゃないの」 あやめが中川の醜い男の女装姿を評す。名探偵を除いた全員が頷いているところから、どうやらこの場にいる人間は皆知っていたらしい。そう言われて見てみれば、厚塗りのぬりかべのような恐ろしい顔は男のものにちがいない。しかし、変装をするにも他に手段があるだろ、と言いたくなるような女装姿である。それにしても、今までどうして誰も指摘しなかったのだろうか。 「個人の自由ですから」 あきらが明るく、謎に答えてくれた。彼女は、とても楽しそうだった。確かにその通り。 「でも、アタシは犯人じゃないわよ」 あっさりと、中川は否定をする。女装がバレたのに、相変わらず女の仕種がやめられないらしい。いや、もしかしたら元からそういう趣味があるのかもしれない。 「あのね。いい加減、その気持ちの悪い女言葉やめてくれませんか」 名探偵は頭が痛くなってきた。頭痛だけではなく、おまけに、もれなく叶き気まで丁寧についてきた。 「あら、そうね。バレでしまったからには仕方がない。実は、私は新ピンカートン探偵社日本支部の腕利き社員で被害者からの依頼でこの島にやってきたんだ」 おいおい。 「…なぜ、女装を」 名探偵が目を点にして、中川に尋ねる。中川は名探偵の問いに重々しく頷く。いつのまにか主人公権は名探偵から中川に移っていた。 「それも依頼の内だ。変装して島に乗り込むように指示されたんだ」 中川は指示が書いてある手紙を面前に差し出した。確かにそこには、『なお、島は来るときには、必ず変装をしてくること』と書かれている。だからと言って、わざわざ女装姿じゃなくても良いと思うのだが。どうだろう。しかし、中川はすっかり自分の女装姿が気に人っているのか、着替えるそぶりさえみせなかった。いや、もしかして元から女装趣味があったのかもしれない。女装癖の有るフランケンシュタイン。何か、壮絶なものを感じるのは間違っているのだろうか。 「山田氏は、心配していたのだよ。自分の愛人が、自分のことを殺すに違いと思いこんでいた。そして、その愛人が彼を殺したんだよ。そう、いつものようにコトに及んでいる最中に被害者を無残にも殺した」 それにしても、見てきたように話す輩だ。もしかして覗いていたのだろうかと疑うほどである。殺されるのをじっと覗いていたならば、それもそれで悪趣味としか言えないのではなかろうか。 「その愛人とは…」 < 名探偵の視線があやめとあきらの上に彷徨う。いったいどちらが、愛人なのだろうか。二人とも、面白そうな顔で中川のセリフを聞いている。どちらが、愛人であったとしてもバレることはないと考えているのは明白だった。 そして、中川はいかにも聴衆を意識した態度で犯人を指名した。そう、これからは中川の独り舞台が待っているのである。これからやってくるはずの、称賛と嵐のような拍手が中川の躯を熱くさせた。 「宮城高次、お前だ。お前が犯人だ。お前は、被害者と同性愛の関係にあったが、それを解消するために殺人に及んだのだ」 名探偵の顎が外れる音がした。いや、名探偵だけではない。他の聴衆も、驚いたように執事の青白い顔を見つめていた。ここから、夢までに見た中川の独り舞台が待っていたはずだった。しかし、そうは問屋がおろさないのが、ならわしである。 「それは少し単純すぎると思いませんか」 執事は無表情なまま、中川を見つめた。中川の指摘にも全く堪えていないらしい。確かに、中川が動機として挙げた同性愛関係の解消ならば、殺さなくても他に手段は色々ありそうではある。 「同性愛を動機にするならば、わざわざ女装をしてきたあなたこそぴったりとくるんじゃないんですか」 執事はせせら笑った。確かにそれも一理あるような気もする。 「それもそうですね。もしかしたら、屍体は世にも珍しい容貌の好み持っていたのかもしれない」 名探偵は、例え動機が違っていても自分の名指しした犯人説を捨てられないことから簡単に同意をする。それにしても、女装のフランケンシュタインが好みという趣味は俄に信じがたい。しかし、世の中には変な好みを持っているひともいないこともない。 「ちっちっち、それは違うな。多くの服装倒錯者は女装することにより、自信が増大し、普通の身なりをしている時よりも自分が男らしく感じるのだよ。しかも肉体関係の点で同性愛である人の占める割合は、ごくわずかしかないと言われているのだ。」 「要するに、中川さんは自分の男らしさに自信がないってことですよね」 あきらがにっこりと微笑んで、だめ押しをするように言った。可愛らしいだけあって、その唇から発せられる言葉は怖い。どうやら、この人物は他人を絶望の谷に突き落とすのが趣味らしい。はっきり言って良いタチではない。 「どうみても、女らしくも見えませんけど」 兄の竜衛があきらを沓めるように言った。しかし全くフォローにはなっていなかったのは言うまでもない。全くどういう兄妹だよ、こいつらは。 「そんなことは解っているよ。私を犯人あつかいしてくれたお返しだ」 宮城はいきなりぞんざいな口調になった。どうやら、こちらが彼の地なのだろう。宮城は自信に満ちた足取りで聴衆の前に進みでた。今度は宮城にスポットライトが当てられるようである。 「私の考えでは、犯人は大道寺あやめ。理由は、卑怯極まりない恐喝だ。彼女は、被害者が正規の手段で財産を手にいれてないことを知っていた。だいたい、名前からして彼女が殺人者である証拠。あやめは伝説中の殺女に通じるとして古来から忌み嫌われた名。殺人者の名前として、これほど似合う名前もないだろう。私は、何を隠そう宮城高次とは仮の名前、実の名はサム・ペキンパー。探偵組合の所属のハードボイルド派の探偵なんだ」 サム・ペキンパーはどこからともなく、よれよれのトレンチコートと中折れ帽を取り出すと、それらを着用する。そして、煙草をくわえるとニヒルに笑ってみせた。 「異人さんだったのか、君は」 名探偵は開いた口が閉まらなくなっていた。それにしても異人さんはないだろ、異人さんは。 「いや、生粋の江戸っ子で」 因みに、江戸っ子とは両親ともに三代東京もしくは江戸に住んでいなければならない。それも、東京と言っても、江戸と呼ばれた範囲内でなければならないらしい。なかなか、難しいものである。 「…なんて、それで名前がサム・ペキンパーなんだ?」 中川が皆を代表して、誰もが聞きたかったことを口にした。すると、宮城いや自称サム・ペキンパーは気取った笑みを満面に浮かべる。よくぞ、聞いてくれましたとでも言いたそうであった。どうやら、誰も彼もがナルシストの塊らしい。見てみたいような、見たくないような光景である。 「その方が、カッコいいじゃないか」 どうやら自称だったらしい。そのことついては、誰も感想を言わなかった。しかし、彼は感想が貰えなくてもあまり気にならないと見える。 宮城の背後に、演出用に出現した電灯の明かりが、なんとなく物悲しい雰囲気を醸しだしていた。が、彼がハードボイルドの世界に浸っていれたのもそこまでだった。 「笑わせないでよ。なんて、恐喝者が金づるを殺さなきゃならないのよ」 あやめは、馬鹿馬鹿しいと首を振った。その口調の冷たさは、南極よりも冷たかった。しかし、ここで相手に負けているようではハードボイルド派の探偵はやっていけないのである。あくまでも、非情を絵に描いた男でなくてはならない。サム・ペキンパーはそっと涙を拭って、応戦体制に入る。 「私は知っているんだ。君は恐喝をするために、この島にやってきた。しかし被害者の方は、君には残念なことにその要求をつっぱねた。そして二人は揉み合いになり、君は被害者を殺してしまったのだ」 だから、どうやって詳しい事を知ったのだろう。一度、誰かその過程を説明してくれないものだろうか。 「ふんっ。よく言うわ。私は真犯人を知っているのよ」 あやめは、靴を鳴らして仁王立ちになるなり、こう叫んだ。いまにも「女王様とおよび」とでも言いかねない感じであった。どうしてこうして、観客の目を気にしている様な演技じみた態度だった。 「誰だ、それは」 サムーペキンパーは、まさかと心の中で叫んだ。そう、ハードボイルド派の探偵は、できるだけニヒルで無口で、冷静沈着でなければならないのである。立ち振る舞いに関して、幾つもの規約があり。ある一定の監査を突破すると、目出度く「ハードボイルド派」の看板が掲げられるのである。イメージとしては、最近流行りのプライバシーマークや、ISOの監査みたいなものと考えて戴ければ問題ない。 「犯人は、弁護士さん。あなたよね。あなたは、被害者の財産を横領していた」 あやめは懐から手帳を取り出し、中身を読みだした。脅迫の次は横領らしい。あとは、何が残っているだろうか。 「な、何を言いだすんです」 藤井は心外だと言わんばかりの口調だった。しかし、フルコースを食べる手は全く止めない。どうやら、彼にとって、食事はとても大事な事らしい。 「証拠はあがってるわ。おとなしく吐いちゃいなさい。他の人の目は誤魔化せても、この美少女探偵江戸川乱子の目は誤魔化せないわっっ」 大道寺あやめこと江戸川乱子はすんなりとのびた見事なおみ足の片方を、テーブルの上でこれ見よがしに高らかと踏みならしてみせた。なかなか、絵になる風景ではある。 「…美少女って年か?」 ほとんどなけやりになった名探偵の声が、部屋のなかに虚ろに響く。名探偵は、次々に正体を表した容疑者達に呆れていた。いったい、何のためにこれほどの数の探偵がこ こに出てくるのか?自問自答したところで、答えは出てきそうもない。それに、これだけで済むのだろうか。名探偵は残りの馬脚を現してない容疑者たちの顔を順繰りに眺め た。そして、最後に名探偵は、現在の主人公役である乱子と目が合う。 「いいのよ。どうせなら、美少女の方が語感がいいじゃないの」 乱子は一所懸命に悩む名探偵・に向かって、ウィンクをしながら投げキッスをした。名探偵は女性と縁が薄いのか、あっという間に顔を真っ赤にさせる。 そんな微笑ましい(?)光景をよそに、藤井は目に見えておろおろし始めた。しかし、それも束の間。今度は藤井が自信ありげな笑みをにんまりと浮かべた。 「わ、わたしよりも、あやしい奴はいる。青柳竜衛、あきらの兄妹だ。二人が被害者を殺した理由は、復讐。被害者はいたいけなあきらをレイプしたんだ。その復讐だよ」 藤井はいつのまにやら新たに作った、ウィスキーのソーダ割りを一気に飲み干して噴せた。本当の予定万らは、藤井はここで決めをするつもりだったがあえなく失敗。 「人間の想像力ってすごいわ」 あきらが拍手をしはじめた。犯罪者と名指しされたと言うのに驚くべき無邪気。どうやら、本当に感心しているらしい。それは、兄の竜衛も同じと見え、あきら同様に感心の眼差しを藤井に向けていた。 「しらを切るきか?他のぼんくら探偵はまだしも、美食家探偵藤井則夫はだまされないぞ」 藤井は、ポーズを取りながら大見得を切った。ぎょろりと、瞳を動かす。なるほど、始終何かを食べているはずだ。しかしながら、食べ物を食べながらの見得を切っても、残念ながらあまり格好良くない。 「だって、僕も探偵なんだもの」 あきらの無邪気な返事。皆の視線が少女の顔に集中する。さすがに、他の登場人物はこのオチだけは考えていなかったらしい。因みに探偵だからと言って、探偵が犯人でない可能性はない。そう、『水戸黄門』ではあるまいし、『探偵』という名詞が葵のご紋付き印籍のかわりにはならない。しかし、この理論がこの場の人間には、今のところは浮かばなかったのは言うまでもない。 「へっ?」 名探偵の間抜けな声。本日、初めの切れ者の名探偵の役柄を返上して、彼は驚き戦くだけに存在しているようなものだった。はっきり言って、これだけは考えていなかったのにと、名探偵は頭を抱えた。どうして、十五才くらいの見た目だけ愛くるしい少女が探偵であると誰が思うだろう。 「清廉潔白探偵事務所の所長の聖玲です。因みに、今日は『少年探偵』です」 と、言うなりあきらは勢いを付けて、身につけていた衣類を脱ぎ捨てる。その下から現れたのは、黒いスーツ姿だった。玲の手にはどこからともなく現れたとしか思えない、白い扇が握られており、隣に控える竜衛を扇で指すと紹介をした。 「で、こっちが執事兼助手の巽」 巽と紹介された竜衛は、軽く頭を下げた。内ポケットから、銀縁眼鏡を取り出して鼻にかける。しかしわざわざ、眼鏡をかけるワケは何なのだろう。 「…普通は配役が逆じゃないのか」 サム・ペキンポーがハードボイルドの掟を忘れて、呆然とした面立ちで言う。確かに普通は、名探偵明智に助手の小林少年はつきものだけれども、反対に名探偵小林少年に助手の明智であることはないはずである。 「これは、普通のお話じゃないんでいいんです」 玲はあっさりと応える。わかったような、わからないような返事であった。登場人物が揃って、鳥が豆鉄砲を食らったような顔をしていたのは言うまでもない。 「それより君は何で、女装をしてたのかね。君も女装愛好者だったのかい」 美食家探偵が尋ねる。彼の手にもいつのまにか、次の新しい鳥のもも肉が握られていたりする。どうやら、これが彼のトレードマークらしい。室内では良いが、室外でも鳥のもも肉を持ち歩いているのだろうか。 「私は、女装愛好者じゃないぞっっ」 未だに、女装をやめない中川が虚しい反論をする。しかし、余り説得力がないのは言うまでもない。 「いいえ、先ほど言った通り、今日は『少年探偵』なだけです」 玲は、他の人には良く解らない説明をする。不親切なことこの上なし。 「…それより、どうやってあのワンピースの下にそんな恰好ができたのよ」 美少女探偵江戸川乱子が不思議そうに首を傾げた。女性らしい質問である。乱子の手には床に投げ出されたあきらのものだった衣類が握られていた。どう考えても、青柳あきらこと聖玲が着ていた白いレースの縁取りがされた黒いワンピースはひざ上の丈だったからだ。確かに謎である。 「それは、企業秘密です。それより、ずっと気になっていたんですけど。僕、実は神田川一生氏とは友人なんてすが、ここにいる神田川警部は全くの別人なんですよ。なぜでしょう?」 玲は乱子ににっこり笑ってみせると、今まで悲しいほどに影が薄かった警視庁猟奇課警部を振り返った。今までセリフすら一言もないのだから、とてつもない影の薄さである。偽物と断定された神田川は渋い笑みを浮かべた。 「ふっ。バレては仕方がないな。私の名は…」 そして、重々しく頷いて神田川が、もったいぶって正体を明らかにしようとした。しかし…。 「いまさら、そんなことはどうでもいいわ。どうせ、あんたも名探偵のひとりなんでしょ」 乱子のセリフに全員が頷くと、それっきりニセ神田川には見向きもしなかった。 「ちょっと、誰か私の名前を尋ねてくれー」 ニセ神田川は悲痛なる悲鳴をあげた。が、二度と彼には晴れ舞台が巡ってくるチャンスはなさそうである。よよよと泣き崩れるニセ神田川の目の前に、同情に満ちた眼差しの玲か見下ろしていた。 「残念でしたね。だいたい、偽名に使った名前が悪いですよ。神田川一生と名乗る人物には、こういう運命が必ず待ち受けているのです」 玲が厳かなる予言でも下すように言った。そして、それまで同情に満ちていた眼差しを消すと、唇の片端をつり上げるような人を馬鹿にした笑みを浮かべたのである。 そして、ふりだしに戻る。 「船頭多くして、船進ますみたいでございますね」 巽がどこからともなく持参した、ティーセットで勝手にお茶会を開いていた。青磁のティーポットから、琥珀色の紅茶が音を立ててカップのなかへ注ぎ込まれる。紅茶で満たされたカップはご主人様の玲の目の前に差し出された。 カップを受け取った玲は、目の前でもめている探偵たちを妙に感心しながら温かく見守っていた。要するに、二人だけ非日常のエアポケットに避難しているらしい。 「…何か凄いなぁ。そうそう見られる光景じゃないよ。神田川警部にもぜひお見せしたかったなー」 玲はにこにこしながら、紅茶をI口含んだ。なんだか、とても楽しそうである。少なくとも、事件の渦中にいる当事者めとるような態度ではなかった。 「神田川さんがご覧になっていたら、それはそれで大変な事になっていたのではございませんか?」 しかし、他の探偵達は楽しいどころではなかった。なぜならば、登場人物が探偵だけしかいないという、恐るべき異常目体になってしまったからである。こんなことになるとは、いったい誰が予想するだろうか。 「どうなっているんのよ、この状況。名探偵ばかりじゃ、話が進まないじゃないの」 乱子はいらいらとしたように、爪を噛む。美少女探偵を名乗るだけあって、彼女はメイド姿からセーラー服姿に変わっていた。個人的に言わせて貰えば、彼女はセーラー服 よりもメイド姿のほうお似合いだったと思う。 「しかし、古今東西の探偵小説では名探偵が犯人だったというオチも数多くあるからな」 中川が自分以外の探偵達の顔をぐるっと見回した。因みに時間も相当経過したのにも関わらず、まだ女装をやめてない。よほど気に入っているらしい。 「じゃあ、誰が犯人なんだ。そうか、貴様が犯人だな。お前だけ犯人扱いをされなかったじゃないか」 自称サムーペキンパーは名探偵を指さした。名探偵は冗談じゃないとばかりに、首を左右に振る。 「そんな無茶苦茶な……私は名探偵だぞ」 名探偵には悪いが、そんな無茶苦茶が罷り通るのだな、この話の場合。 「あのー、わたくしめも指名されてないんですけど」 ニセ神田川の発言はあっさりと無視された。神田川と名乗っただけでこんなにも影が薄くなるとは、彼も考えていなかっただろう。 「待ってください。だいたい、みなさんはずいぷんとご立派な推理があったじゃないですか」 玲がいかにも、わざとらしい口調で尋ねる。いやにゆっくりとした口調と、顔に張り付いているようなアルカイックスマイル。 「あんなもの、相場だよ。相場」 と、自称サムーベキンパー。その言葉に探偵たちは、同意見だったらしい。どうやら、彼らは登場人物表を見て犯人の目星をつけただけと見える。こんなんで、本当に良いのだろうか。 「そうよ、セオリーに則った推理ですもの。外れる方がおかしかったのよ」 乱子が力いっぱい言う。とても、悔しいらしい。しかし、それで本当にいいのか。 「…みなさま、確率の問題でもおやりになっているのでございましょうか?」 巽が小声で、隣に座っている玲に囁いた。確かに、そんな気がしないでもない。しかし、そんなので犯人を決めていたら、まるで○曜ワイド劇場を見ながら俳優で犯人を当てるのとそうかわらないような気がする。 「そうかもしれない」 玲が嘆息をした、その時。どこかで、何かが切れるような音がした。その音は部屋の隅からしたものだった。そして、そこにいたのはニセ神田川だった。ニセ神田川は、鬼気せまる表情でどなり始めた。 「くそっ。いつまでも、無視してんじゃねーよ。このヘボ探偵たちめ。犯人は、この俺。動機はな、この俺が大事にしていたクリスティーナちゃんを汚した復讐よ。そうさ、あの子は天女のよう。俺の理想の女性だった。あの時、俺が探偵の依頼を受けたとき彼女を連れてこなければ、あの野郎に見初められることもなかったんだ。俺はクリスティーナちゃんの仇を取ったんだっっ」 どうやらニセ神田川はとことん無視された事で、とうとう切れてしまったらしい。あからさまに目の色がおかしかった。 「クリスティーナって誰?」 乱子が胡散臭そうに、にせ神田川に尋ねた。 「幼女のダッチワイフ」 ニセ神田川が、そう答える。趣味が悪い。悪すぎるぞ、ニセ神田川。ニセ神田川の返事を聞くと探偵たちは、円陣を組むとニセ神田川に聞こえないように事件内容の審議会を開いた。 「動機にしては品位が…」 「話として…」 探偵たちは暫く話し合っていたが、結論が出るとニセ神田川の方を振り向き、こう合唱した。それはそれは見事な合唱だったことは言うまでもない。 「却下っっ」 「な、なんてだ」 ニセ神田川は、残念なことに簡単に自分の告白を否定されてしまった。あまりのあっけなさに、ニセ神田川は呆然とする。呆然しているニセ神田川に探偵たちは、口々に却下された理由の述べはしめた。 「そういう犯罪は、あまり好みじゃないのよね」 乱子が鼻で笑う。彼女は学生鞄の中から、爪磨きを取り出すと先程噛んで傷めてしまった爪を磨き始めた。 「複雑な人間関係も無縁だし」 自称サムーペキンポーは、煙草に火をつけるとあらぬ方向を向いた。その角度が二番、自分の顔が恰好良く見えるからである。ハードボイルドは自分のスタイルにも気をつけなければならないのだ。 「せっかくの、嵐の孤島の上に古びた屋敷という古き良きシュチュエーションが台無しだな」 中川が肩を疎ませて首を振る。しかし、女装姿のままなので何とも不気味で恰好がつかなかった。 「そうそう、私としてはもう少し高尚な犯罪を味わいたいね。だいたい、被害者が美女ではないなんて、何たることだ」 藤井はよほど被害者が美女でほしかったらしい。でも、被害者が美女でなかったことは、ニセ神田川の責任でもなんでもないような気がする。 「でも、そこまで馬鹿馬鹿しい動機を思いついたトコロは評価できるんじゃありません」 玲が妙なトコロで感心をする。 「いやいや、これでネクロフェリアなロリコンなら、まだ救いようがあったんですけどね」 と、名探偵が締めくくって、ニセ神田川の罪の告白への感想は全ておしまいだった。そして、八人の探偵たちは三十点と赤いペンで書かれた紙をニセ神田川に手渡すと、彼から完全に背をむけてしまった。この話は、犯罪批評だったのだろうか。謎である。 「俺は罪を告白しても、こういう扱いを受けるのかっ。神よ何故なんです。俺が何をしたんだと言うんです」 だから、偽名のせいだってば。 ニセ神田川は悲痛そのものの声で叫ぶと、嵐の中に出ていってしまった。その後どこかで、雷鳴をバックにした悲鳴と崖から落ちていく人影が見えたような気がしたが、たぶんそれは気のせいだろう。 「それで、いったい誰が犯人なのでございますか?」 巽はぜひとも後ろから殴ってやりたいほどに、妙に沈着冷静だった。 「僕、考えたんですけど。もしかして、この騒動の犯人は被害者なんじゃないかなー」 玲は額の中央で分けている前髪をかきあげる。これはこの人物の癖らしい。 「自殺殺と言うことか」 「いいえ、文字通り被害者が犯人だと思っています。ただし殺人の犯人じゃないですけどね」 「そんなわけないじゃない」 乱子が抗議の声をあげる。その声に他の探偵たちも同感だと言わんばかりに頷く。被害者が犯人であるなんて、そんなことがあってはならない。探偵たちの内の確固たる信念が、そう言っていたのである。 「そうだ、屍体がどうやって被害者のフリをするんだ」 しかし、ここでは常識が通用しないことを探偵たちが没念していたのは言うまでもない。そう、世の中侮れないのである。 「いえいえ、さっきの地の文で気になるところがあったんですよ。『そして、八人の探偵たちは三十点と赤いペンで書かれた紙をニセ神田川に手渡すと、彼から完全に背をむけてしまった』と、いう場所ですよ。登場人物表を見て下さい。ニセ神田川を除くと、僕ら七人しかいないはずなんですよ」 玲は作者から原稿用紙を横取りすると、件の箇所にい赤ペンで線を付けた。そして、登場人物表と原稿用紙を探偵たちの前に広げてみせる。確かに、そこには八人の探偵が云々と書かれていた。 「と、言うことは」 全員の視線が八人目の探偵に向けられた。平凡な服装に平凡な顔。八人目の探偵は目立たないことにかけては、人一倍だった。 「はっはっは。ばれちゃったか」 異様に明るい声。彼は胸のところに探偵と書かれた札を下げていた。そして、今度は屍体と書かれた札を掛けなおす。そうして見れば、先程まで隣室で倒れていた屍体。その人に間違いなかった。どうやら、いつのまにか紛れ込んでいたものと思われる。 沈黙の嵐が、元被害者以外の登場人物に吹き荒れた。しかし、そのことに気がつかない元被害者は酒々と喋り続けた。 「いやいや、十分堪能させて貰ったよ。嵐の孤島に探偵の集団。そして、謎の屍体を登場させてみたらどうなるかと思ってね。思っていた以上に楽しんませて貰ったよ。どうしたのかね。皆さん顔色が悪いようだが」 明るい元被害者が、自分の顔を凝視したままその場に固まってしまった探偵たちに誘しげに声を掛けた。彼は別に何も罪悪感のかけらすらもないらしい。 探偵たちが一斉に自分を取り戻す。そして、こう元被害者に向かって言った。 「ふっ、ふざけるなー」 見事な混成二部合唱。次の瞬間、探偵たちは我を忘れて元被害者に襲いかかった。悲鳴、怒号、物が壊れる音。この日、初めて探偵たちに協調性と言うものが現れたのだった。 数日後、地方紙の隅に、こんな記事が掲載された。
探偵がいっぱい…『名探偵登場』がしたかったんです。(笑) |


|
|
|
|
Copyright (C) 2006. Mangougasa. All Rights Reserved. |